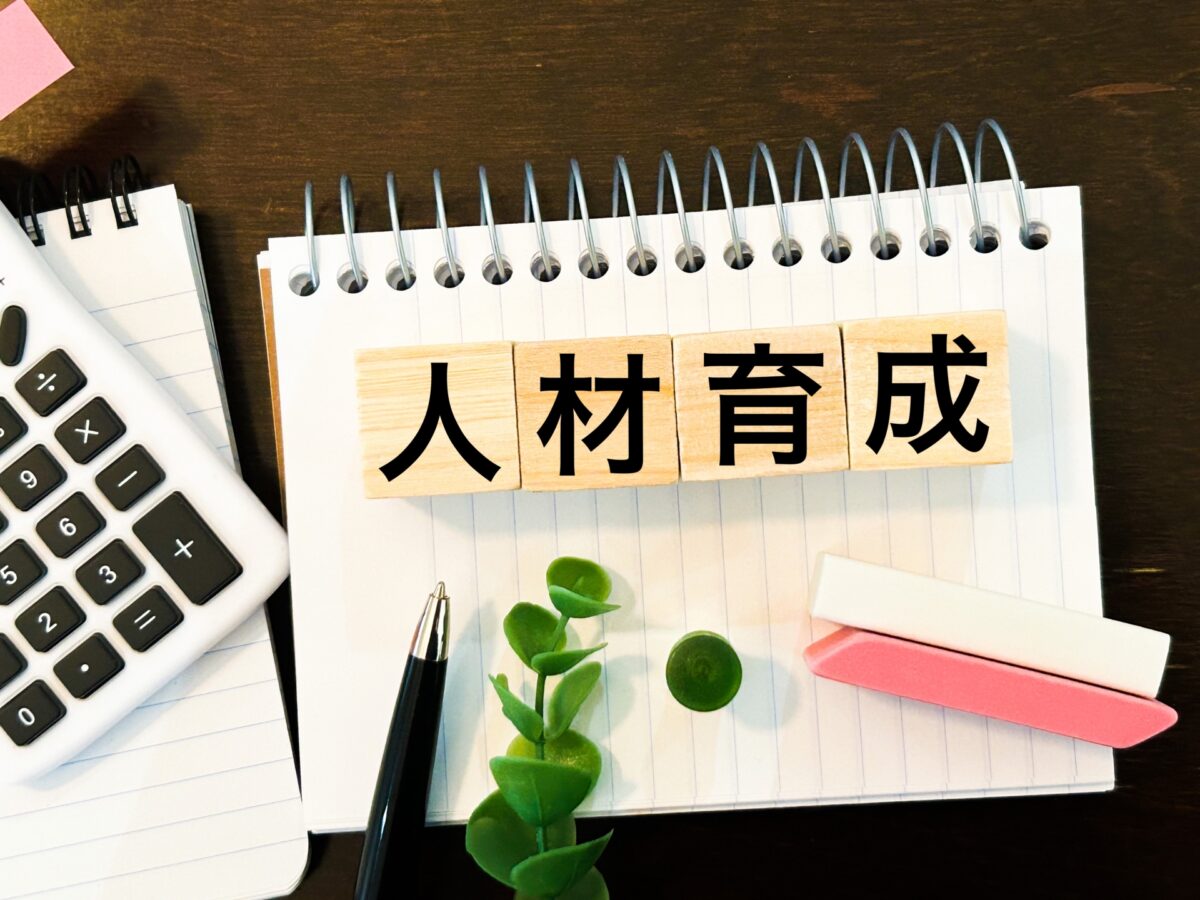税理士は社会福祉法人の経理担当者の人材育成も可能か?
社会福祉法人にとって経理担当者の育成は弱点の一つです。
何故なら、多くの社会福祉法人は、会計制度を理解している人材が法人内にほとんどいないからです。
筆者は、社会福祉法人の経理部の管理職を14年勤めましたが、その経験を踏まえて人材育成のポイントを記載します。
目次
離職率と向き合う必要がある
経理部に限ったことではありませんが、筆者の経験上、離職の理由のナンバーワンは「疎外感」と「不信感」です。
また、離職率の低い法人の特徴は、「各人がやりがいをもって働けてる。つまり、個人に適切な裁量権があり、それが周囲から尊重されている。」です。
管理者が、管理を放置したり、業務を丸投げし担当者の業務に関心を持たなかったりすることはNG行為です。
法人に都合があるように、担当者にも都合があります。担当にやって欲しいことを伝え日々折り合いをつける必要があります。経理業務が分からない管理者は、以下のような抽象的なミッションでも構いません。
・現状、経理規程にある試算表提出日に間に合っていないので、間に合わせるようにしたい。
・先日の行政指導検査で指摘されたこの事項を解決したい。など
担当者は、その時代によって望むものが違います。そしてそれは日々変わります。
・今はとにかく実務の経験を増やしたい。
・家族の介護の都合で定時に帰りたい。
・いくら残業しても良いので今は給料を増やしたい。など。
担当者とギブ&テイクを通して、信頼関係を構築し、お互いが前向きに働けるように尽力するのは、管理者の役目です。
管理者から、「冗談じゃない。」「そんな暇ない。」「子供じゃないんだから」という反論が聞こえてそうですし、その気持ちも分かります。筆者も現役時代は随分悩みました。しかし、管理者が経験値を上げて、器を大きくすることが、離職率を下げる一番良い方法だということをまずご理解頂きたいのです。
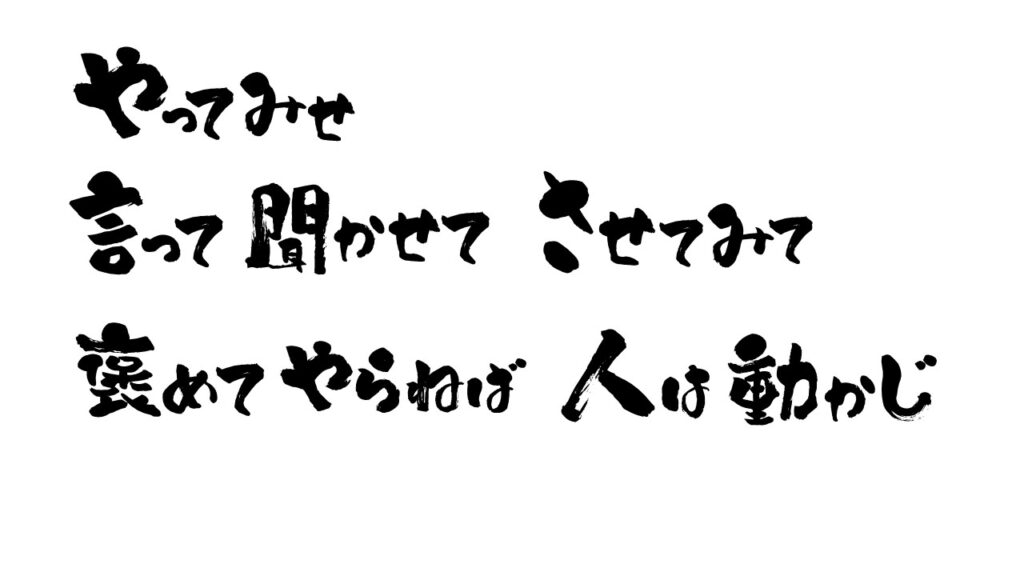
経理は普遍的な教育が必要
社会福祉法人の経理は、株式会社より細かく制度的です。補助金や助成金など多額の公費を受け入れる性格から、お金の使い道が厳格に管理されるためです。
したがって、社会福祉法人の会計基準や国が出している通知など公のルールだけでなく、定款や経理規定など内部的なルールも理解する必要があります。
また、経理担当者はどの法人にも通用する普遍的な知識の習得を好みます。
一般的に税理士にとって、一番貢献できる人材育成はこの部分です。
その法人がどのような規模でどのような事業を行うかによって、知るべき知識が異なります。
筆者は、在職中「社会福祉法人の会計制度について」という動画を撮影して、入職者の研修期間中にそれを見せて、問題を解かせて、経理職員全員が同じ経理の基礎知識を持てるような仕組みを作りました。作成時に手間がかかりますが、一度作れば時空を超えた育成ができるためお勧めの方法です。
法人サイドでこういうのが作りたいという仕様が言えれば、外注も可能でしょう。
経理の実務はパソコンソフトの教育が必要
経理は制度的な知識があれば勤まるかというとそうではありません。その法人独自の運用がたくさんあるからです。
まず、最初にその法人が採用している会計ソフトの使い方を知る必要があります。我々税理士でも使ったことのない会計ソフトは、慣れるまで大きなストレスがかかります。会計ソフトそのものの機能に加え、その法人が望む設定を理解しなければなりません。
社会福祉法人の経理の中途採用の社員は、企業会計の会計ソフトは使ったことがあるが、社会福祉法人の会計ソフトは初めてという方がほとんどです。
筆者は、在職中に仮想の簿記一巡の研修教材を用意して、新入社員に操作を覚えさせました。
1,パソコンに会計ソフトをウンロード
2,マスターと勘定科目を設定
3,営業取引を入力
4,決算整理仕訳を入力
5,決算書の作成
6,自分が作成した決算書と模範の決算書を見比べて修正
自分のペースで何度でも練習できるため、操作自体はすぐにできるようになります。

経理の実務は、運用の教育が必要
経理の実務は、たくさんの運用方法を決める必要があります。例えば、証票の保存方法や保存場所などは、その法人によって全く異なります。
実は、経理の人材育成で最も気を付けなければいけない点はここです。なぜならば、運用の方法は自由であり、指導検査で是正されることはありません。言い換えれば、「どんなに非効率なやり方でも構わない。」ということになります。
担当者が、正しいと思ってやっているやり方が、とても非効率で無駄が多いということは、本当に良くあります。そして、担当者の業務が効率的か非効率化を比較する機会はほとんどありません。
筆者は在職中に、運用マニュアルを作成させて担当者全員が共有していました。
法人内の隣の拠点のやり方を見て、自分のやり方を考えるという簡単な話です。
よくあるお話として、退職が決まったら慌てて引継マニュアルを作成して、あまり検証もしないで次の方に渡すケースが多いと思いますが、それを日常的に作成して随時更新しているだけの話です。
マニュアルには管理者の目が入りますし、マニュアルを変える時には議論になりますので、統一的な意識と業務効率の向上の機運が高まります。
しかし、担当者が作成するマニュアルは税理士のような専門家が作るものでないので、必要最低限で良く、時間のかけ過ぎは効果の少ない業務になります。
経理の実務は属人的になりがち
いくら管理者が正しい教育をしても、24時間担当者に付き添うことはできません。
経理業務はたくさん人数のいる現場の支援員などと違い、各拠点に1名とか法人全体で数名というケースがほとんどです。
結論から言うと、とても孤立しがちで、業務が属人的になりがちです。
お金に関する不正が起きやすい環境も、属人的な環境です。
各人は基礎知識や業務に対する意欲が違いますし、拠点によって事業内容が異なるため、マクドナルドのような全員共通の完全なマニュアルを作成することもできません。
一定のミッションの中で、各人に裁量権を与えて、品質の均一化と向上を目指さなければなりません。
筆者は、経理担当者だけで行うWEBのミーティングと内部監査を活用しました。そもそも法人内に経理担当者だけが集まる定例の会議があればそこを活性化すれば良いと思いますが、実施している法人は少ない印象があります。
定例のミーティングの目的は、担当者に串刺しの意識を持ってもらうこと。内部監査は、管理部門が指示した内容が現場で実現しているのかを確認して会計責任者に伝えることです。
担当者に一人で業務をやっている訳でないという意識を持ってもらうことが重要です。代替が可能な環境の構築は、急な体調不良や退職に対応できるだけでなく、不正防止にも役立ちますので、一人しか業務が分からない環境は避けるべきです。

まとめ
会計や税務には答えがありますが、人材育成に答えはありません。
筆者は、社会福祉法人の管理職として14年間で数十名の経理職員の採用と人材育成を行いましたが、最も難しく、最もやりがいを感じた業務でした。
主観的な印象ですが、14年のうち前半5年より後半5年の方が思い通りの育成ができました。思い通りの育成が言葉にできないのが、もどかしいのですが、人材育成にノウハウや法則はあるのだろうと思います。
一方、社会福祉法人の現場にとって会計は、大事なのは分かっているけど、難しくて良く分からない。現場は、利用者支援が優先で経理なんて後回し。施設長は正直あまり経理に関心がない。とうのは、よくある話で、本音なのではないでしょうか?
1法人1拠点ならば、規模が小さいので一人の力技で何とかなるかもしれませんが、1法人複数拠点、数十億規模の法人になると組織を作りチームプレーをしないと業務はガタガタになり、そのガタガタは経営に帰ってきます。
「風通しの良さは組織の力」といわれます。逆にいうと、「風通しの悪さは非効率の源」と言えます。
当事務所が社会福祉法人から経理職員の人材育成を受注した場合、以下の事を行います。
1,経理担当者に疎外感や不信感を抱かせない配慮。
2,会計制度の教育を正しく理解させること。
3,必要最低限のIT教育をすること。
4,運用を担当任せにしないで、組織的に工夫していくこと。
5,属人的な環境を避け、不正防止とワークシェアをすること。
6,拠点間の垣根を外し、風通しの良い組織を目指すこと。
人材育成は簡単ではありませんが、経理は経営を明らかにする根源です。
「より良い福祉はより良い経営から」人材育成のお役立て頂ければ幸いです。