社会福祉法人の監事監査の現状と問題点は何ですか?
日本には社会福祉法人が約2万法人あり、監事は1法人につき2人以上ですから、少なくても4万人以上の監事が存在します。
「社会福祉法人とのお付き合いの中でお願いされて…」とか、「以前から名誉職的に特定の法人の役職者が代々引き継いで…」という話をよく聞きます。
分かりますが、少し待ってください。監事はそのような軽い役職ではありません。
今回は社会福祉法人の監事監査について取り上げたいと思います。
目次
社会福祉法人の監事監査の3つの特徴
筆者が社会福祉法人で20年間監事監査を受け、その後税理士として監事監査を外から見てきた印象として3つの特徴があると思います。
まずは、そこから紹介いたします。

監査がピックアップ方式にならざるを得ない。
社会福祉法人の監事監査は数時間から数日という短時間で行われる傾向があります。
公認会計士の監査人監査でも同様ですが、監査は全ての項目を見るのではなく、限られた時間の中で抜き打ち検査のような性質があります。
時々、現場の方から網羅的に見なくて良いのですか?という疑問が出ることがありますが、限られた項目しか点検できませんので、方法としては問題ありません。
監査は犯罪を捜査している警察のような不正を探す役割というより、不正が起きにくい仕組みを確認しているため少しのサンプルで良いことがあります。
したがって、監事が範囲や方法を決めることが必要で、最も重要なポイントになります。
監事は法人側から提出された資料に基づき監査せざるを得ない。
監事は社会福祉法で調査権がありますので、自らの意思で積極的に情報を収集することができますが、最初は法人側が事前に用意した資料で監査しますし、現実的にはその範囲で終了することがほとんどです。
したがって、事実上は提出された範囲で監査しますので、もし、法人側に情報を秘匿されてしまうと、気が付かずに監査が終了してしまう恐れがあります。
監査が形骸化しがちな傾向にある。
監事監査は、少ない予算と限られた時間の中で行うケースが多く、法人が用意した監査報告書という書面にサインするだけといった、形骸化しがちだと言われています。実務的には、いわゆる御用監査などといわれ、問題視されています。
以下の項目で何故そのようになってしまう理由を紹介します。
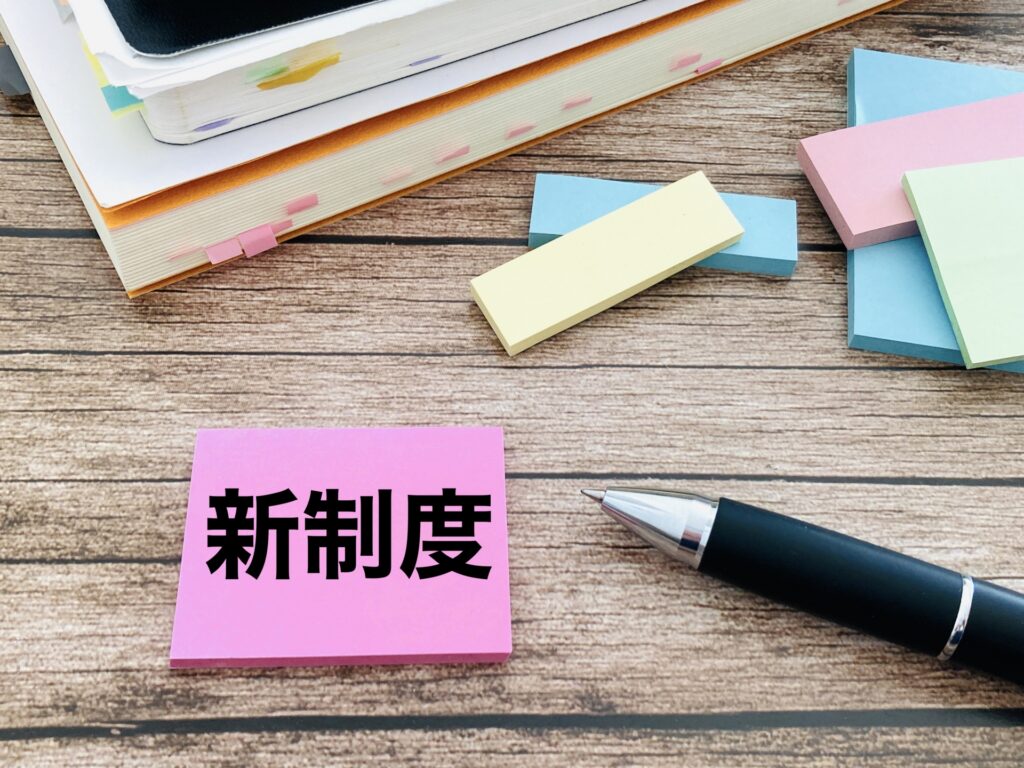
法改正後の社会福祉法人の監事監査の制度的な内容
平成28年の社会福祉法の改正後にある監事監査の制度的な内容をいくつか紹介します。
監事はどんな人か?
監事は2人以上で、以下の方が必ず含まれます。
(1)社会福祉事業について識見を有する者
(2)財務管理について識見を有する者
資格要件ですので、その区分で各々の領域を監査するという意味ではありません。監事は法人全体に対して責任を持ち、監査報告書を一人ずつ出すこともできます。
また、社会福祉法人は株式会社と違い、株券や持ち分がありません。したがって、もし役員が法人の財産を私的に流用しても、株主代表訴訟ができません。
このような場合、会社の財産を取り返せるのは監事となり、社会福祉法人の利用者や職員の生活を守る最後の砦として重要な役目を担ってる方々という事ができます。
監事監査は何をするのか?
監事は評議員から委任を受け、次のようなことをチェックします。
理事が不正をする。(又は不正の恐れがあると認めたこと。)
理事が法令若しくは定款に違反する。(又は著しく不当な事実があると認めたこと。)
つまり、監事は、独立した立場で「理事が」「適法・適切に職務を執行しているか」「評価している」ということになります。
監事の代表的な権限
社会福祉法人の監事は、その社会福祉法人を守るために、非常に大きな権限が法律で与えられています。
・監事はいつでも、理事や職員に報告を求め、調査する権限があります。
・法人に著しい損害が生じる恐れがあるときは、行為の差し止め請求権があります。
・理事会の招集権があり、意見を述べられます。(議決権はありません。)
・監事は職務執行費用の請求権があります。
・法人が理事を訴える場合は、法人に変わって監事が法人を代表します。
監事の代表的な責任
平成28年の社会福祉法改正により、監事の責任も重くなりました。
・任務懈怠による損害賠償責任を負います。
・悪意又は重大な過失による損害賠償責任を負います。
・善良な管理者の注意義務による損害賠償責任を負います。
・特別背任罪、収賄・贈賄罪、不法行為に対する過料の適用などの罰則が加わりました。

監事監査の問題点
社会福祉法人の監事監査で一般的に言われている問題点をいくつか紹介します。
監事への報酬が安すぎる問題
東京都が集計した監事の報酬状況では、報酬の平均は125,955円(中央値80,000円)で17.3%の法人は無報酬でした。
引用:r6-3-10-remuneration-of-auditors-pdf
上場企業の非常勤監査役の報酬(社外監査役の場合)は、日本監査役協会による調査によると、中央値が200万円から500万円であるとされていますし、厚生労働省が集計した社会福祉法人の会計監査人監査の報酬は400万から500万程度ですので、監事監査の報酬は法的責任の重さに対し、監事の報酬水準は極めて低いと言わざるを得ません。
年間報酬が10万円程度で、責任感を持ってきちんと監査をして欲しいとか、監事である公認会計士に専門家責任を負わせるのは、あまりにも無理があり、当然に監査が形骸化する要因の一つと言われています。
利害が対立しないという問題
税務調査や指導検査の検査官は、税金や補助金を通して社会福祉法人と利害が対立しますので、緊張感のある調査や検査になりますが、監事はその法人がその法人の意向でお願いして引き受けてもらうため、法人と利害が対立せず、法人の意向に沿った監査になりがちであるという問題が指摘されています。
御用監査といわれ、監査が形骸化する理由の一つと言われています。
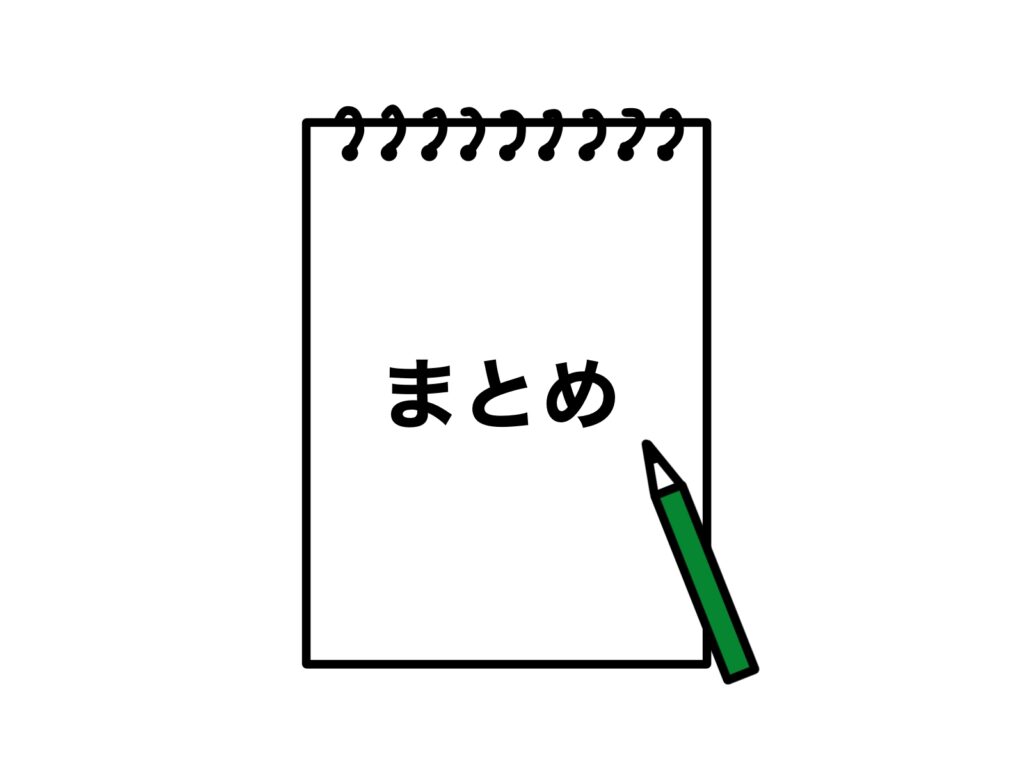
まとめ
(1)監事は理事の業務をチェックします。法令違反や不正の事実だけでなく、著しい不当性や不正の疑いも含みます。
(2)監事は報酬が低く、選任する理事と利害が対立しないため、監査が形骸化しがちという御用監査問題が指摘されています。
(3)監事は、理事に不正があった場合には、法人を代表して守るという重要な役割があり、独立した立場で調査権や業務の差し止め権、理事会招集権など重大な権限が与えられています。
(4)改正社会福祉法により監事の損賠賠償責任や刑事罰は重くなりました。
如何でしたでしょうか?
監事は監査を行うだけでなく、理事会に出席したり、場合によっては入札の立ち合いに参加したりしますので、時間的にはかなり拘束されます。
監事が理事会を連続して2回以上欠席すると、指導監査では文書指摘になると言われています。確かに、自治体の検査官は理事の欠席より、監事の欠席の方がより深刻な問題と捉えている傾向があり、法人側も理事会の日程調整の際に、監事の欠席は避けたいため、監事の都合が最も優先されるという話をよく聞きます。
監査は、健康診断的な意味があると言われています。健康診断も項目が増えたり、検査内容が高度になったりすれば費用は高くなります。監事の費用はそうなっていないことが多いのではないでしょうか?
仕方ないという理由で、監査を形骸化させるのでなく、アクティブに機能させて、自分達では入手できない有益な情報を入手して法人の経営に生かすことが、より良い福祉を行うため、社会福祉法人が生き残るために必要だというのが筆者の意見です。
当事務所は、監事と連携して監事監査を機能させる実践的な研究をしています。
監事の方に監査の方法をレクチャーしてもらいたい、方法を提案してもらいたい等、監事監査の進め方でお悩みの法人は、ご相談頂ければ幸いです。

