思っていたより重要な社会福祉法人の予算制度とは?
社会福祉法人の財務諸表の開示情報で資金収支計算書を眺めていると、超過予算の決算書をよく見かけます。
予算が形骸化してしまっている社会福祉法人も残念ですがよく見聞きしますし、実務をやっていた経験がある人は、予算を置き去りにして実績重視になる実情は理解できると思います。
しかし、予算制度は重要な側面がありますので、今回は社会福祉法人の予算制度を取り上げます。
目次
社会福祉法人の予算制度の概要
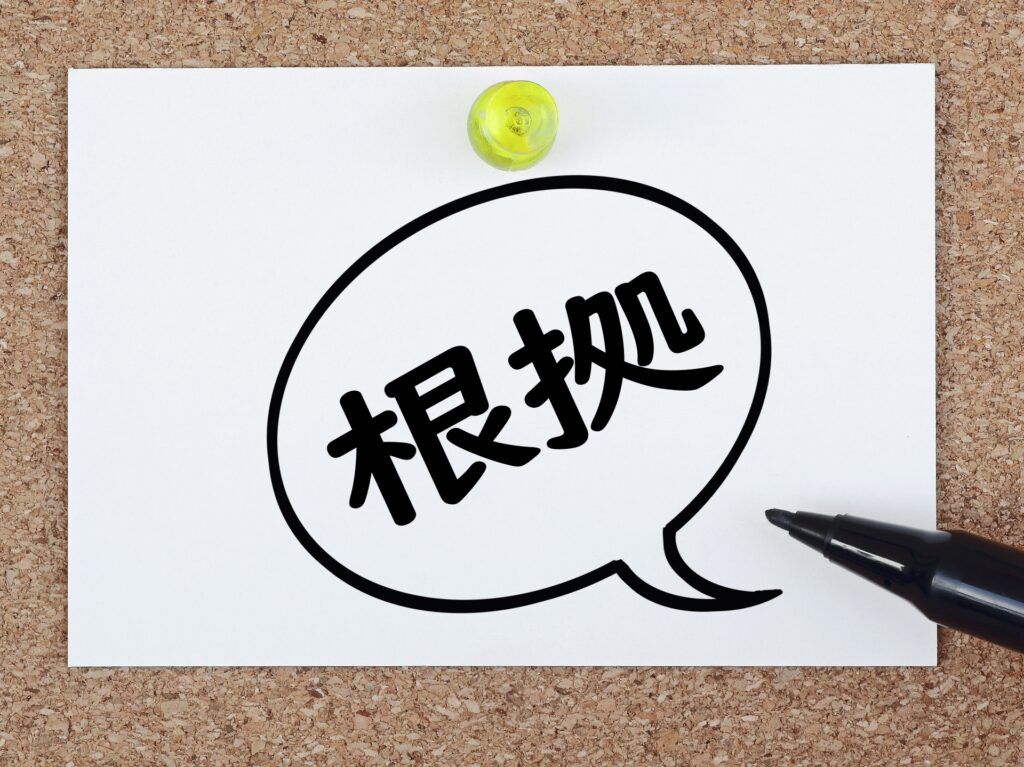
予算制度の根拠は、課長通知といわれる運用上の留意事項、定款、経理規程の3つです。
社会福祉法人は事業計画に基づいて予算を作成しますが、予算書は理事会の承認を受けた公式な書類です。
社会福祉法人の財産は私的財産でなく公共的な性質がありますので、役員の会議である理事会が唯一財産の使い道を決めることができます。ただし、煩雑性から一定の範囲で理事長にその権限を委任することがあります。 その一つが予算制度です。
したがって、原則として委任された範囲でしかお金を使うことはできませんので、予算を超過した支出は、職務権限を超過した危険な状態であると言えるのです。
また、予算は資金収支計算書に転記され、決算書上の資金収支計算書の約半分を構成します。
社会福祉法人会計は資金収支計算書をトップページに配置し、最も重視します。
歴史的に、官公庁の単年度決算で収支計算を意識した会計に影響を受けているためです。
そういう観点でも予算は重要な役割を負っています。
社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項(課長通知)の論点
まずは制度上の注意点ですが、制度ですので全法人共通事項になります。
(1)予算の単位は拠点単位です。任意でサービス区分単位で行うこともできますが制度上は必要ありません。
(2)資金収支計算書の科目で作成します。任意で事業活動の科目で作成することもできますが、制度上は必要ありません。
(3)年度の途中で乖離が見込まれる場合は補正予算を編成する必要があります。ただし、軽微な範囲で留まる場合は、補正予算を編成しなくてもよく、この軽微な範囲の基準は、法人側で主張できますが、あらかじめ決めて経理規程や経理規程細則などで文書化しておくことが望ましいとされています。
社会福祉法人の定款上の論点
定款上の注意点は、法人によって変えることもできますが、ほとんどの法人がモデル定款で認可を受けてますので、事実上全法人共通事項となります。
(1)予算の承認者を定款で定めます。基本的には理事会ですが措置法40条の税制優遇を受ける法人は評議員会にする必要があります。
(2)事業年度開始前に定める必要があり、閲覧環境に置く必要があります。
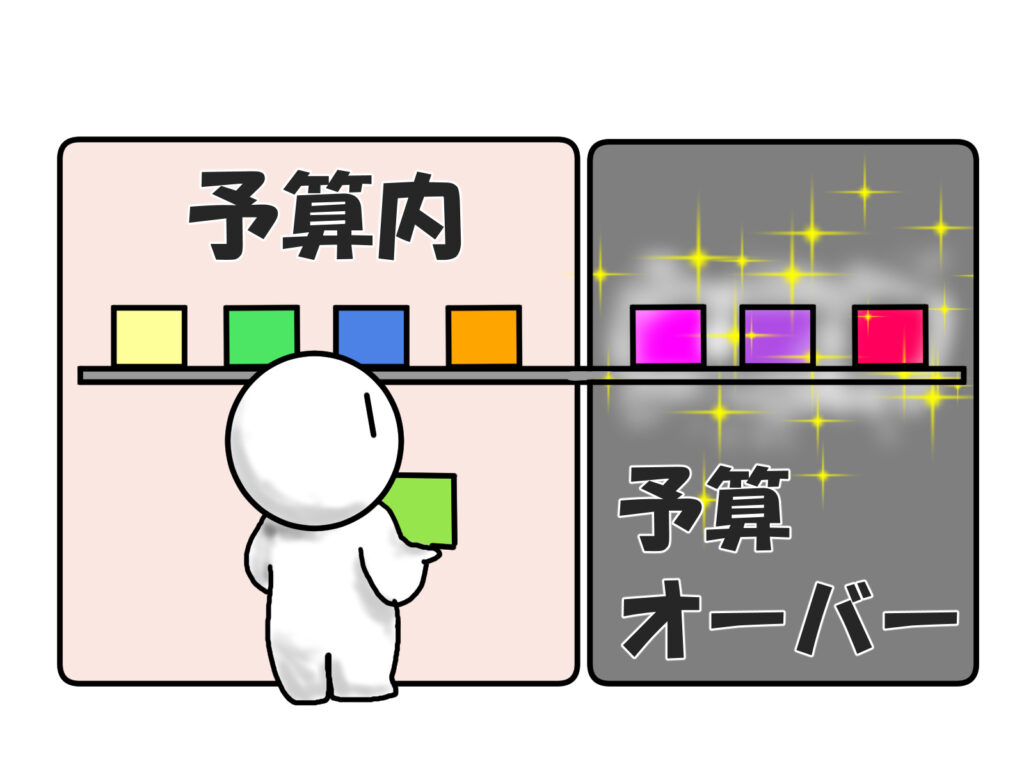
社会福祉法人の経理規程上の論点
経理規程上の注意点は、上記の注意点を受け入れた上で、細かい点を補足しています。経理規程は法人の自主性により作成できますが、ほとんどの法人はモデル規程をベースに作成しており、モデル規程と乖離する場合は、指導検査で是正するように指導されますので、事実上全法人共通となります。
(1)予算管理責任者を定めます。会計責任者を予算管理責任者にできるため兼務可能です。
(2)科目流用ができます。立てた予算が超過する場合、まず中区分間の科目の範囲で流用します。これは理事長の権限ですので、稟議書(起案書)で承認を受ける必要があります。
(3)予備費流用ができます。科目流用で足りない場合は予備費流用を検討します。これも理事長の権限ですので稟議書が必要で、更に、流用額の理由と金額を理事会に報告しなければなりません。
(4)科目流用も予備費流用でも対応できない不足が生じた場合は、補正予算となります。予算は、理事会議案になります。
予算に関してよくある質問
最終補正予算のタイミングについて質問が多いです。予算の執行は4月1日から3月31日までの期間です。それに対して、決算の理事会は翌年度の6月ですので、4月1日から6月の決算理事会迄の間に最終補正予算を行って良いか疑問が出ます。
もし、6月の決算理事会において、決算書の議案の一つ前で最終補正予算の承認を受けることができるのであれば、事後承認でありながら決算書の資金収支計算書の実績数値を転記すれば100%整合させることが可能で、予算統制の意味がなくなってしまう懸念があるからです。
実務上、指導検査などでは2つの見解があるようです。
(1)3月31日迄の支出ですから、3月31日迄に最終補正予算の承認を受けるべきです。それ以降はいわゆる事後承認となりますので、流用で対応すべきであり、補正予算は災害などやむを得ない場合以外は行うべきでないという見解。
(2)もう一つは、超過予算は、決算理事会直前でも良いので最終補正予算を行ってほしいという要請。超過したものは軽微なものを除き認められません。したがって、決算理事会直前でも良いので最終補正予算で承認を受けて超過状態を解消して下さいという見解。
筆者の肌感覚では、3月の理事会で翌年度の当初予算と当年度の最終補正予算の承認を受けている法人が多い印象です。また、その後4月1日以降に補正予算を組むか否かは指導検査で指導されている法人は、行うという考えの法人が多いです。
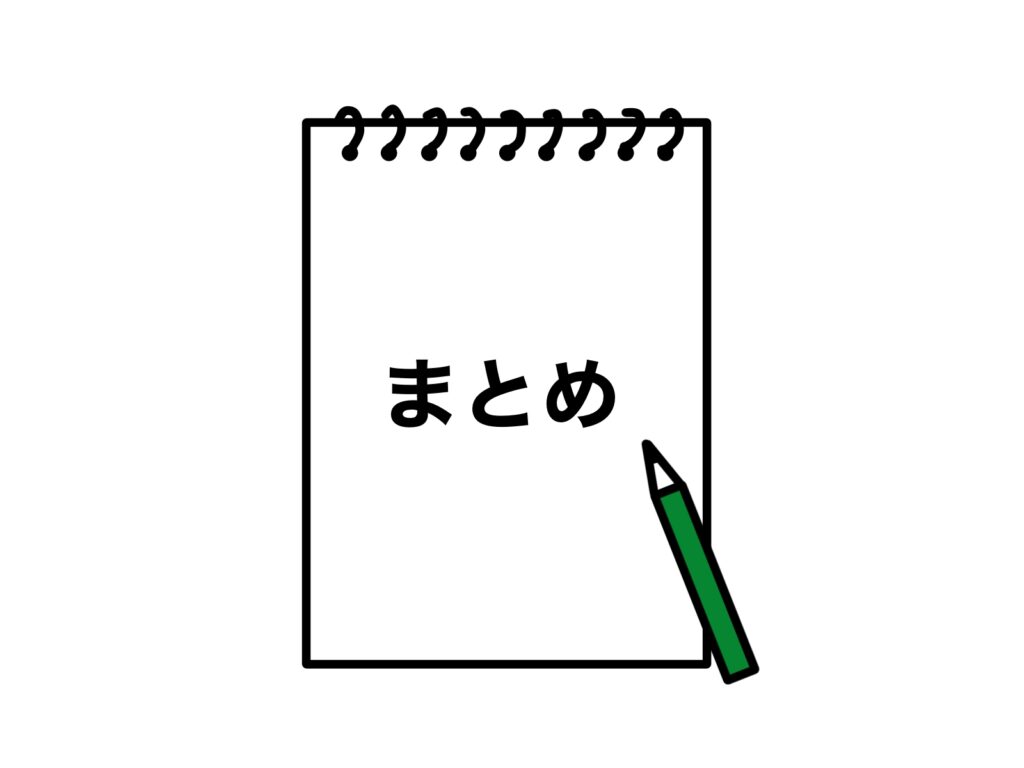
まとめ
予算制度は、職務権限の委任でもありますので、その範囲を超えているのは危険な状態です。
予算の根拠は、課長通知、定款、経理規程の3つです。
予算の運用は、立てた予算の範囲、中区分の科目流用、予備費流用、補正予算の順番です。
年度末以降決算理事会迄の補正予算は、行うべきでないという見解と、積極的に行うべきという見解が分かれています。所轄官庁の見解に合わせると良いと思います。
予算が正しく行われていない社会福祉法人は多数あります。確かに筆者の経験でも、指導検査で予算の事を言われることは少ないという印象があります。しかし、指導検査ガイドラインでは文書指摘にできますし、公開されている指導検査結果で予算が指摘されていることもありますので、いつ文書指摘されてもおかしくありません。
社会福祉法人は私物的な法人でなく、多額の公費が入る公共性がある法人ですので、手間はかかりますが、指摘される前に、正しく運用することをお勧めします。
事業の計画を行い、毎月実績を確認することは、経理の基本中の基本です。
当事務所は、大規模な社会福祉法人予算の正しい運用の支援をした実績があります。予算制度でお悩みの法人はお気軽にご相談ください。

