社会福祉法人に個人が土地等を寄付した場合の措置法40条と取消の可能性とは?
社会福祉法人は非課税法人というイメージがあると思います。
当然、ほとんどの規定は社会福祉法人本体の税金が優遇されるということなのですが、社会福祉法人でなく社会福祉法人に関係した外部の人が税制優遇を受けられるという規定もあります。
今回は、税理士がよく質問される、措置法40条と言われる、個人が社会福祉法人に土地等を寄付した場合に課税が優遇される所得税の特例を紹介します。
目次
税制優遇の略語

税制優遇の論点は、一般的な名称として略語のようなものが付く時があります。
土地等を寄付した場合の税制優遇は、租税特別措置法40条1項に根拠があることから、「措置法40条」などと言われることがあります。
一方、別規定で、土地を売却した場合の課税の特例は、租税特別措置法33の4に根拠がありますが、「措置法33条」とは呼ばれず、「5,000万控除」などと呼ばれることが多いようです。
今回は、土地シリーズでは比較的有名な、前者の「措置法40条」規定を解説します。
措置法40条規定とは?
社会福祉法人は、歴史的には資産家からの寄附を元手に事業を行ってきました。制度的にも寄付を想定しています。株式会社と違い出資を受け入れられないためです。
寄附ですから、反対給付や対価性のない性格になります。したがって、所有性や譲渡性もありません。
資産家が私財である土地を社会福祉法人に寄附し、その上に施設整備の補助金により建物を建設するのは、典型的な施設開設のパターンですが、ここで問題になるのは、いわゆる「みなし譲渡課税」です。
「みなし譲渡課税」とは、個人が土地などの財産を法人に寄附した場合、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されてしまうことです。
国税庁は、公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらましで「これは個人から法人に土地などの財産が無償で移転するときに、個人に帰属する値上がり益に対する所得税を精算するための制度的要請によるものです。」と説明しています。
引用国税庁ホームページ:A4-12 租税特別措置法第40条の規定による承認申請|国税庁
正論ですが非常に厄介な側面があります。

この9,000万円の値上り益の課税は厄介です。一般的に、土地は時の経過とともに高額になる傾向があります。先祖代々伝わるようなものを相続したり、長期的保有を目的に購入したりしたものが多いと思いますが、このような土地は取得価格(簿価)が比較的低く、現在の時価はそれより高いというケースが多いと思います。
このような土地の簿価と時価の差は含み益となり、たとえ無償で寄附した場合でも、みなし譲渡として課税されてしまうのです。 もし、通常の売却(譲渡)した後なら、売却代金である1億円というお金を受け取りますので、課税されてもその受け取ったお金の一部で納税できるので問題ないと思いますが、寄附の場合、売却代金である対価を受け取りませんので納税資金が発生しません。したがって、納税資金を別途用意しなければならないことになります。これでは、寄附者の負担が重すぎて、寄附を妨げてしまうことになりかねません。
社会福祉法人は寄付を想定した制度設計をしていますので、寄付を妨げることは避けたいのです。そこで、国は、社会福祉法人に寄附した場合には、このみなし譲渡益部分を別規定で非課税にする必要がありました。
税の優遇は、デメリットもあります。この適用を受けるためには、税務署側の承認を受ける必要があり、寄附をする個人も受ける法人も手続きがかなり煩雑なことです。
社会福祉法人の方々は、その法人の規程作成の際に参照したモデル定款やモデル経理規程に租特法第40条の適用を受ける法人と受けない法人の選択をしたと思いますが、この論点の規制のことです。
規程の相違内容は、税制優遇を受ける代わりに規制を強化する趣旨ですので、この適用を受ける法人は申請時だけでなく、将来に渡ってより規制を受けることになります。
例えば、予算は通常、理事会の決議事項ですが、措置法40条適用法人は評議員会決議事項に格上げされるなどがあります。
定款に関しては平成29年3月29日に厚生労働省より定款例の通知が出ています。
厚生労働省ホームページ参照: 租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号の要件を満たす定款の例について
国税庁ホームページ参照:社会福祉法人定款例(租税特別措置法第40条適用版)|国税庁

優遇の取り消しの可能性
優遇の対象は、寄付者が本来払わなければならない税金で、非課税の要件が土地を社会福祉事業に使うことですので、その土地が社会福祉事業に使われなくなった(非課税の要件を満たさなくなった)ならば、その時に寄付者又は受け入れた社会福祉法人のいずれかに課税されます。
この性質から、社会福祉事業に使われなくなるまでの課税の繰り延べ規定と説明する方もいます。その説明は、理論上は合っているのですが、実務上は、税の取戻しが必ず起こる課税の繰り延べ規定とは分けて考えた方が良さそうです。
例えば、寄付された土地を社会福祉法人が売却した場合は、社会福祉事業に使わなくなりますので取り消し事由に該当し、土地を社会福祉事業に使用する前の売却なら寄付者に課税、土地を社会福祉事業に使用した後の売却には社会福祉法人に課税されます。
(参考)国税庁ホームページ
ただ、本来寄付者に課税されるものですので、売却時に寄付者が死亡しており、死亡した年の翌年から5年を経過したならば、時効(除斥期間)が成立し、課税権がなくなるという実務事例があります。この場合、税の取戻しが起こらないことになりますので、理論的な話と実務的な話は異なる可能性があります。
取り消しに関する厚生労働省Q&A
社会福祉法人が措置法40条適用法人に定款を変えた場合に起こりうる問題について厚生労働省からQ&Aが出ています。
うっかり定款を変えてしまっても直ちに非課税承認が取り消されるわけではない等の記載があります。
(引用)厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 平成29年1月24日 事務連絡
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000149668.pdf
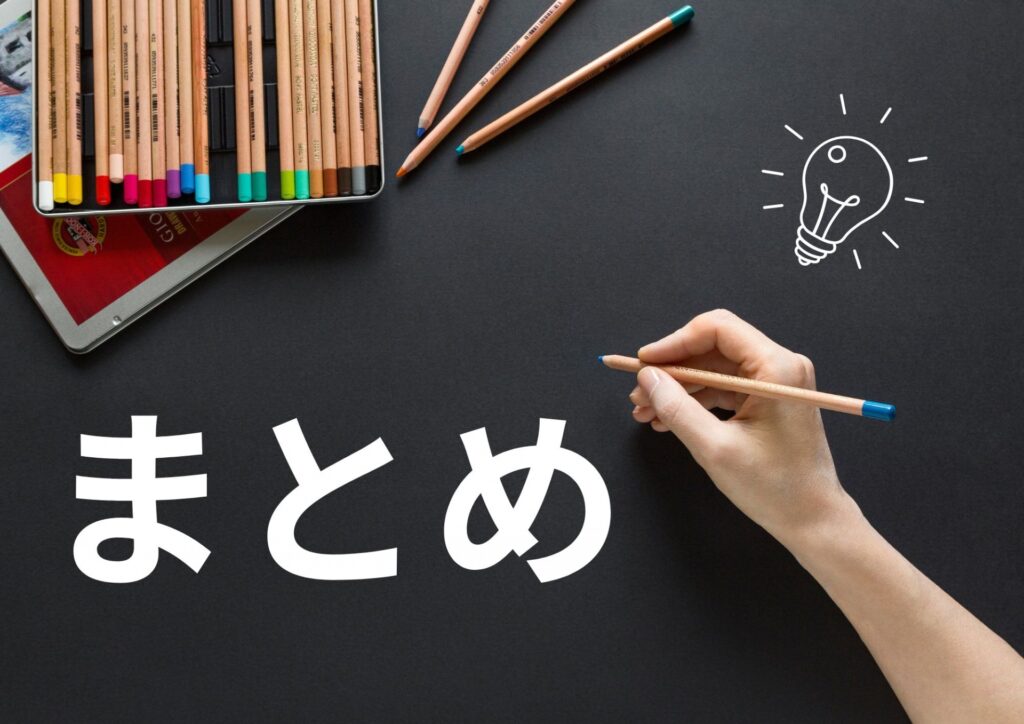
まとめ
(1)個人が社会福祉法人に土地を寄付する場合は含み益には課税されます。
(2)含み益に課税されないために措置法40条の規定が用意されています。
(3)措置法40条の適用を受ける場合、寄付を受けた社会福祉法人は規制を受けます。
(4)非課税とされた含み益部分は課税の繰り延べ的な性格があります。
(5)厚生労働省からも措置法40条の適用に関する定款例やQ&Aが出ています。
この優遇を受ける場合の規制内容は法人の理事会や評議員会の運営方法も含み、かなり複雑です。
また、この規定を適用すると、後戻りできない規制を受け続けるというデメリットがあるため慎重に検討すべきでしょう。
当事務所はこの規定の支援を通常の顧問業務とは切り分けして、成功報酬型の支援の可能性がありますので、ご検討の方はお気軽に相談下さい。

