社会福祉法人専門の税理士を選ぶ際の5つのポイントはコレだ!
社会福祉法人の皆さんにとって、もし社会福祉法人専門の税理士が存在したら興味があると思います。以前はあまり見かけませんでしたが、平成28年の社会福祉法人会計基準の改正以後は社会福祉法人専門の税理士を見かけるようになりました。
今回は、どのように社会福祉法人専門の税理士を見極めれば良いかを簡潔にご案内します。
目次
本物の社会福祉法人専門の税理士を見極める5つのポイント
一般的な税理士を選ぶポイントとして例えば値段が安い、親身に質問に答えてくれるなどが思い浮かぶと思います。しかし、社会福祉法人を専門とする税理士を選ぶポイントはガラっと変わってきます。
今回は、5つほどそのポイントをご紹介しますので是非参考にしてください。
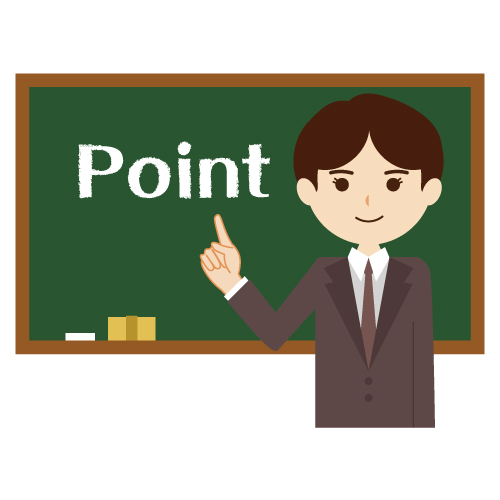
1.社会福祉法人に対する取り組み姿勢を見極めよう
社会福祉法人は、透明化が進んでおりすべての法人で財務諸表開示システムにより事業内容や決算情報の公開が義務付けられています。
一方、税理士も税理士検索により名前や事務所が公開されていますが、取り扱い業務に関しては公開が強制されていません。したがって、事前に調べる時は、まず、ホームページなどで社会福祉法人の業務の記載のある税理士を候補にすることをお勧めします。
次に、ホームページの対象法人をよく見て下さい。得意な法人を記載しているはずです。株式会社以外にも特殊法人はたくさんあります。例えば、いわゆる公益法人等と言われる社会福祉法人・公益社団法人・公益財団法人・学校法人・宗教法人・NPO法人などが存在します。
公益法人等全般に特化した税理士もいますし、社会福祉法人のみに特化した税理士もいます。社会福祉法人だけに特化している税理士が一番お勧めです。
さらに、社会福祉法人の中でも、保育事業に特化した税理士もいれば障害福祉事業に特化した税理士もいます。税理士は得意とする事業の違いにより、提供するサービスの品質が異なります。ミスマッチが起きないように、自法人が営む事業に最もマッチした税理士を選びましょう。
2.税理士に自己紹介をきちんとしよう
社会福祉法人は情報が公開されています。社会福祉法人に強い税理士は当然そのような情報を把握してきます。したがって、公開情報では分からない情報を中心に伝えましょう。
市区町村内にすべての施設がある場合と都道府県に施設が跨る場合には、所轄官庁も異なりますし、指導検査の状況も自治体によって異なります。過去の検査状況を伝えた上で以下のような内容を意識しましょう。
(1)経理業務の業務フローはどのようになっているか?本部集中か拠点分散か?
(2)証票類は紙ベースか電子化が進んでいるか?
(3)本部機能は確立しているか?
(4)経理スタッフは何名で、どこの拠点で誰がどのような役割分担で業務を行っているか?
(5)仕訳数はどの位で、感じている課題は何か?
(6)過去に会計事務所に委託していた業務で過不足を感じていたか?
(7)法定監査が入っていれば、どのような監査手続きが行われているのか?
(8)監事監査上の課題は何か?
(9)理事会や評議員会からの要望はあるのか?
などを伝えると良いと思います。
しばしば伝統的に行ってきた業務が必要のない業務だったりします。自己紹介が要領よく正確に伝えられると、税理士が何をお手伝いすべきかが分かるので良いと思います。

3.税理士の実績に関する質問を投げかけてみよう
一般的に、社会福祉法人を扱える税理士はあまりいません。
社会福祉法人が対応できると表明している税理士は、それなりの実績があると思いますので、その実績について質問してみましょう。
(1)関与した年数…長ければ長いほど制度改正の変遷などを知っており、規定の解釈も高スキルです。
(2)関与した法人数と法人規模…多ければ多いほど実務事例を知っており高スキルです。
(3)関与した業務内容…税務顧問、監事や職員経験など多ければ多いほど高スキルです。
(4)業務のうち社会福祉法人業務が占める割合…100%に近いほど高スキルです。
(5)関与したことのある事業内容…保育・介護・障害など多いほど高スキルです。
(6)社会福祉業界の同業者団体の加入状況…多いほど情報収集能力に優れ高スキルです。
上記の質問をすると、社会福祉法人の業務が得意な税理士はスラスラと答えるはずです。
4.税理士にやってほしいことを具体的に伝えよう
家電を買うときに量販店に行ったことがある方は多いと思います。「パソコンを買いたいなら、いくら位の予算で買いたい。」と事前にイメージしてから行くと思います。店員さんにも「何をお探しですか?」とか「ご予算はどの位ですか?」などと聞かれると思います。
この最初のイメージをもって頂きたいのです。「何をお探しですか?」「ご予算はどの位ですか?」
パソコンなら調べる手段が幾らでもありますので、イメージしやすいのですが、税理士を探すときは調べる手段がなく、このイメージがしにくいのです。
イメージを考える上での参考は、再調達コストがお勧めです。
社会福祉法人の会計と税務業務は、究極的には自法人で全て行うことができます。これを「完全自計化」と定義し作業を洗い出します。自前職員で「完全自計化」を実現するために何人分位のコストがかかりそうか想像できるとなお良いです。これを「完全自計化コスト」と定義します。
そこから、外注したい作業を選定するのですが、外注するより自法人でやった方が効率のよいものがあります。それを「自計化領域」と定義します。「完全自計化」-「自計化領域」=「外注領域」となります。理論的な「外注領域コスト」が認識できるのもこのタイミングです。
次に、「外注領域」を複数の税理士に伝え見積もりを取り、複数見積もりを比較し、最良の見積もりと「外注領域コスト」を比較して、契約先を決定しましょう。
もし、この選定プロセスが自法人でできない場合は、選定プロセスだけを社会福祉法人に特化した税理士へ依頼を検討する方法もあります。税理士にとってはさほど難しくない業務ですし、法人にとっては本来必要ない無駄な報酬を長期的に払うより建設的なコストと言えます。
ただし、外部の税理士しか得られない情報もあることを考慮して下さい。他法人のやり方など自法人では到底思いつかないノウハウを持っている可能性があります。
5.お互いにコスト削減の意識を持とう
税理士はサービス業といって良いと思いますので、報酬は主に人件費になります。
税理士は、納品物に対して手間がかかればかかるほど、高額の報酬を要求しなければならなくなります。したがって、報酬の本質は納品物の品質でなく手間であることをご理解下さい。逆に言うと、高品質でも手間がかからなければ、報酬を下げることができる可能性があるのです。
例えば、提出期日に約束した資料を渡してくれない。何度も何度も請求しなければならない。請求しても一度でなく、違う人からバラバラに提出されて何度も作業に取り組まないといけないなどは、典型的な無駄手間の例です。
最初の報酬設定は、仕訳数や申告書の数など形式的な要素にならざるを得ませんが、契約する前に、税理士の手間を省くことに協力するので、実現したら報酬の見直しをしてもらう可能性を伝えておくと良いと思います。コスト削減意識のない税理士はお勧めしません。
税理士の手間を省く一番良い方法は、DXといわれる情報の電子化です。中には電子化アレルギーでDXに消極的な税理士もいますが、そのような税理士はお勧めしません。
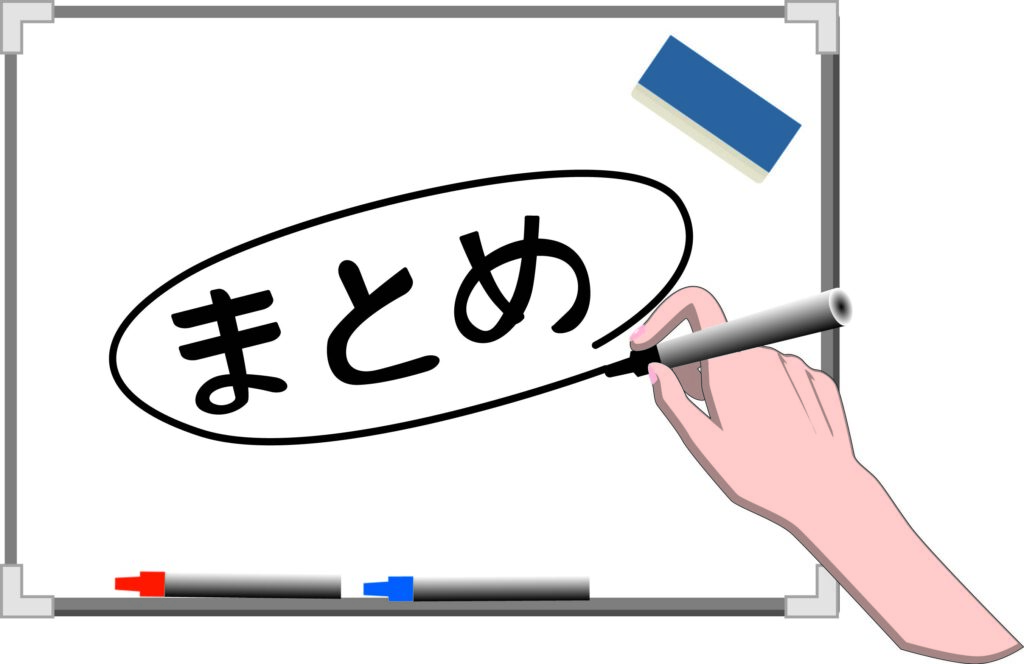
まとめ
社会福祉法人専門の税理士の見極め方を解説してきました。税理士なら誰でも社会福祉法人業務にしっかり対応できるというのは誤解です。
もし担当者が税理士であって欲しい場合は、契約前にそれを伝える必要があります。一般的には税理士が担当した方が、スキルが高く、報酬も高くなる傾向がありますが、そうでない場合もあります。
実績があるのは実は代表税理士だけで、ほかの方は全く経験のない会計事務所も存在しますので担当予定の方のスキルを契約前に確認しましょう。
また、ネット上で社会福祉法人に対応できる税理士と紹介されているマッチングサイトは、税理士が広告費などの手数料を払い、業者サイドで作成した情報を実力とは関係なく、仲介目的で掲載しているものがありますので、ご注意下さい。
以上、社会福祉法人の立場に立って、しっかり対応できる税理士を見極めるポイントを解説してきました。優秀な税理士を探すのは簡単ではありません。
「話が違う」とか「思っていたのと違う」とならないように、みなさんの法人に合った信用できる税理士探しに、お役立ていただければ幸いです。
当事務所は、正真正銘の社会福祉法人専門の会計事務所です。上記のようなお悩みがあればお気軽にご相談下さい。

