社会福祉法人における非課税取引(社会福祉事業編)
社会福祉法人の消費税の非課税を理解するためのカギは、限定列挙された非課税取引13個のうちの7番目の規定に基づく介護サービス・社会福祉事業を理解することです。
今回は、後半の社会福祉事業の対象取引を条文ベース(令和7年3月時点)で紹介します。
本文に、誤解しやすい「類する事業」と「類するもの」に黄色のマーカーを付しています。
資料集ですので、条文が苦手な方は、こちらの記事は読まずに非課税取引についてのご紹介(全体編)の記事のみを読んで全体像を把握して下さい。
目次
社会福祉事業に関連する非課税の範囲
解釈の根拠規定は以下になります。
(1)消費税法6条
(2)別表第2‐7のロ・ハ
(3)消費税法施行令14-3(別表2-7の類するものの範囲)
(4)消費税基本通達6-7-5(別表2-7のロの国税庁の説明)
(5)タックスアンサーNo.6215(別表2-7のハの国税庁の説明)
別表第2‐7の条文構造
イ、介護保険事業
介護保険事業編を参照 社会福祉法人における消費税の非課税取引(介護保険事業編)|立花淳一税理士事務所
ロ、社会福祉法2条の社会福祉事業
→社会福祉法又は基本通達6-7-5へ
ハ、社会福祉事業に類する事業として政令で定めるもの
→消費税法施行令14-3へ

基本通達6-7-5の社会福祉事業の説明
社会福祉法2条に規定する社会福祉事業です。このように、税法が他の国法の概念をイコールの関係で利用することを借用概念といいます。
反対語は、税法の固有概念です。その場合は、社会福祉事業とはという定義が税法の中に別の意味で展開します。
(1)第一種社会福祉事業
イ、生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
ロ、児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
ハ、老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
二、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業(障害者支援施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
ホ、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設を経営する事業
へ、授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業(授産施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
(2)第二種社会福祉事業
イ、生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
ロ、生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(認定生活困窮者就労訓練事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
ハ、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業又は乳児等通園支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター又は里親支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
ホ、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あっせん事業
へ、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
ト、老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
チ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
リ、身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
ヌ、知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
ル、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
ヲ、生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
ワ、生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
カ、隣保事業
ヨ、福祉サービス利用援助事業
タ、(1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成を行う事業
(3)更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業
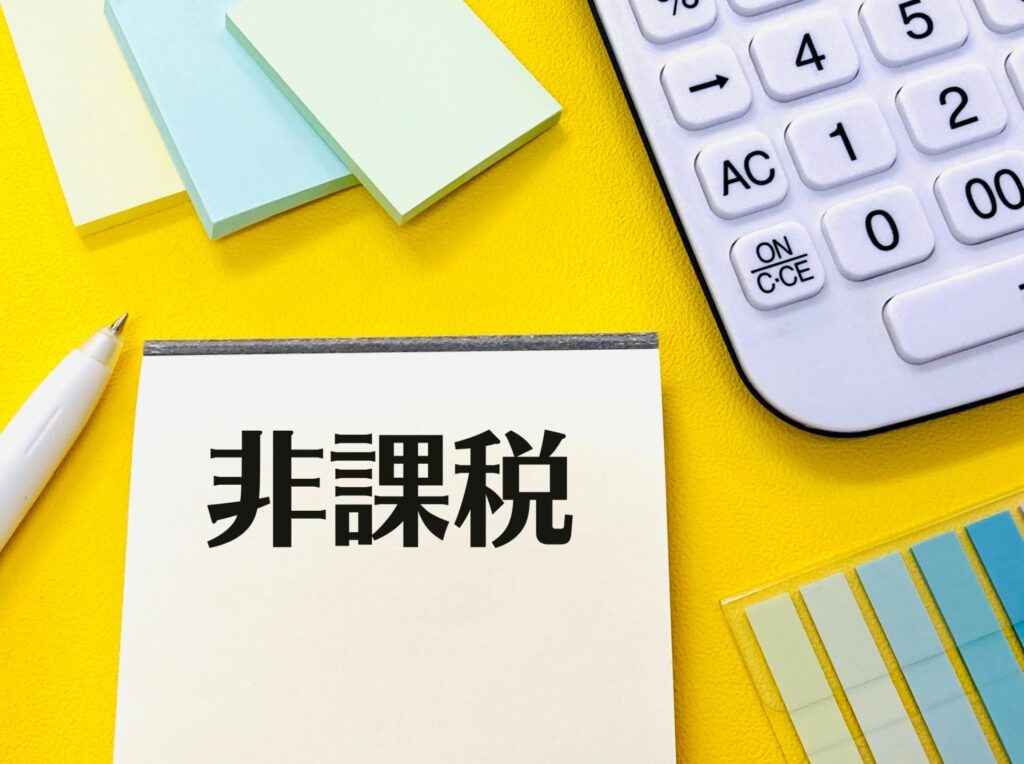
施行令14-3の条文構造
社会福祉事業に類する事業の範囲
(1)児童福祉法に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等および同法に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等(平成17年厚生労働省告示第128号に定める資産の譲渡等)
(2)児童福祉法の規定に基づき指定発達支援医療機関が行う一定の治療等
(3)児童福祉法に規定する一時保護
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同法に規定する介護給付費等の支給に係る施設障害福祉サービスおよび知的障害者福祉法の規定に基づき同園がその設置する施設において行う同法の更生援護
(5)介護保険法に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等(平成18年厚生労働省告示第311号に定める資産の譲渡等)に限る)
難解事例:介護保険法115条の46第1項のうち、同法115条452項の地域支援業を市町村が委託した場合は、この規定により非課税です。(ちなみに同法45条1項は施行令14-2告示307号により非課税)
(6)子ども・子育て支援法の規定に基づく施設型給付費等の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等
(7)母子保健法に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等
(8)老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業のうち一定の事業として行われる資産の譲渡等
(9)さらに、上記(8)に掲げる事業に類するものとして、次に掲げる事業のうち、その要する費用の2分の1以上が国または地方公共団体により負担される事業として行われる資産の譲渡等(平成3年厚生省告示第129号に定める資産の譲渡等)についても、消費税が非課税となります

平成3年厚生省告示第129号の条文構造
社会福祉事業に類する事業の1つの類するものの説明
(1)居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業
(2)施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与する事業
(3)居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を、施設に短期間入所させ、養護する事業
(4)身体障害者、知的障害者または精神障害者(注2)が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業
(5)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する被爆者であって、居宅において介護を受けることが困難な者を施設に入所させ、養護する事業
(6)身体に障害がある児童等(注3)に対してその者の居宅において入浴の便宜を供与する事業
(7)身体に障害がある児童等(注3)に対してその者の居宅において食事を提供する事業
(注1) 身体に障害のある18歳に満たない者、知的障害の18歳に満たない者、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害のある方を含む)、身体上もしくは精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のある65歳以上の者等(これらの者を現に介護または養護する者を含む)、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子もしくはその者に現に扶養されている20歳に満たない者、65歳以上の者等のみにより構成される世帯に属する者、同法に規定する配偶者のない男子に現に扶養されている20歳に満たない者もしくはその者を扶養している当該配偶者のない男子または父および母以外の者に現に扶養されている20歳に満たない者もしくはその者を扶養している者
(注2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害のある方を含む)
(注3) 身体に障害がある児童、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、身体上もしくは精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のある65歳以上の者等または65歳以上の者等のみにより構成される世帯に属する者
(注4) 消費税が非課税となるかどうかを判断するに当たり、その事業が社会福祉法に規定する社会福祉事業等に該当するか否かについて疑義が生じた場合には、その事業を実施する地方公共団体等にご確認下さい。
引用元:No.6215 社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲|国税庁

まとめ
別表2の7番目の後半にある社会福祉事業による非課税取引を説明してきました。
介護保険法のように、総合支援法に基づく資産の譲渡等は非課税となっていないため、総合支援法の事業で社会福祉事業に該当しない事業に対して何らかの手当が必要でした。
ここで注意したいところは、社会福祉法の社会福祉事業とは別に、社会福祉事業等に類するものという「類する事業」と、社会福祉事業に類する資産の譲渡等の一部に類するものという「類する事業に類するもの」の2つの類するものという概念(黄色マーカー)があることです。
特に後半の「類する事業に類するもの」は書き方が抽象的で、どの事業に当てはめて良いのかが分かりにくいので注意してください。この規定でときどき問題になるのは、社会福祉法の公益事業に該当する障害者総合支援法の障害者日中一時支援事業などです。
通所系は、「施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与する事業」に当てはまることが多いと思います。
社会福祉法人の社会福祉事業の非課税判定はこの記事で十分でしょう。
当事務所は、社会福祉法人専門の会計事務所です。消費税に関してお困りの方は、お気軽にお問合せ下さい。


