今更聞けない、社会福祉法人の「新会計基準」を分かりやすく解説!
社会福祉法人は会計が特殊で分かり難いということはよく言われます。
理由は、税金を受け取る社会福祉法人は、我々が日頃慣れ親しんでいる「企業会計原則」でなく「社会福祉法人会計基準」で処理しなければならないためです。
現在の社会福祉法人会計基準は、平成23年の導入時に「新会計基準」と言われたものです。しかし、実はもう一つ「新会計基準」があったことをご存じでしょうか?
一般的な、社会福祉法人会計基準の説明は、公的機関などから多く公開されていますので、一旦お任せして、今回は、誰も知らない社会福祉法人会計基準の歴史を古代・中世・近世・現代と歴史感覚で説明します。
目次
1.古代「会計要領時代」
現在の社会福祉法は、昭和26(1951)年3月に社会福祉事業法として制定されました。
会計に関しては、昭和28(1953)年3月18日「社会福祉法人の会計について」という通知が出されました。いわゆる、「会計要領」と言われるものです。
また、私立児童福祉施設は、昭和29(1954)年5月10日に別の通知が出ており、対象外とされていました。
この時代の会計は、非常にシンプルで法人全体で決算を行うという概念がありません。
「会計要領」の特徴
(1)一般原則として、正規の簿記の原則と明瞭性の原則があります。
(2)勘定科目は別表により指定されています。
(3)減価償却費は計上しても差し支えないとあり、補助金を受けた部分は計上できないとあります。
(4)特別会計という簿外の会計を設定できます。
(5)収益事業で生産をする法人は原価計算を行うこととあります。
引用元:・社会福祉法人の会計について(◆昭和28年03月18日社乙発第32号)
「私立児童福祉施設要領」の特徴
(1)実質的会計方式は現金主義
(2)予算主義
(3)収支の命令者と現金出納者の兼務禁止
引用元:・私立児童福祉施設の財務事務の取扱について(◆昭和29年05月10日児発第231号)

2.中世「経理規程準則時代」
昭和51(1976)年1月31日「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」いわゆる「経理規程準則」が通知されます。
また児童福祉施設に関しては、昭和42(1967)年4月14日「児童福祉施設における措置費の経理について」がいわゆる措置費経理が通知されました。
この時代の会計は、施設会計が中心で、一つの法人が異なる会計基準で処理をすることが当たり前でした。この時代も法人全体で決算を行うという概念はありません。
「経理規程準則」の特徴
(1)一般原則に、真実性の原則と継続性の原則が加わりました。
(2)本部会計と施設会計の会計単位別会計として定められました。
(3)減価償却の計算を行わない規定になりました。
(4)収納した金銭は、一旦取引金融機関に預け入れる規定が定められました。
(5)随意契約の規定が定められました。
(6)借入金や基本財産は本部で一旦経理することになっていました。
(7)共通経費の按分基準が定められました。
引用元:・社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について(◆昭和51年01月31日社施第25-2号)
「措置費経理」の特徴
(1)都道府県の指導検査を受けることが定められました。
(2)使途(支出対象経費)の費用科目一覧が定められました。
引用元:・児童福祉施設における措置費の経理について(◆昭和42年04月14日児発第194号)

3.近世「旧社会福祉法人会計基準時代」
平成12(2000)年2月17日に措置費制度から利用契約への改正に対応するために、「社会福祉法人会計基準」が通知されました。この基準の通達により実務界は、新社会福祉法人会計基準の対応と言われていました。
この時代に初めて、同じ会計基準で処理をするという概念と法人全体で決算を行うという概念が出ました。
しかし、例外も多く、実現する法人と実現しない法人が共存することになりました。
引用元:福祉 – 社会福祉法人会計基準の策定について(平成12年2月17日社援第31号、平成12年2月17日社援施第6号を含む)
適用範囲
(1)原則として全ての社会福祉法人
(2)措置費施設のみの経営法人及び経理規程準則以外の適用法人は除く
(3)病院会計準則適用法人も除く
特徴
(1)公益性を維持しつつ、自主的な運営ができる仕組み目指している。
(2)損益計算の考えを導入し、減価償却方式を取り入れる。
(3)本部会計と施設会計の区分をなくし、法人全体の法人単位会計
(4)資金収支計算書により予算及び決算を作成
(5)資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表の3帳票と財産目録の構成
(6)経理規程の作成が義務付けられました。
(7)定款に定めた経理区分、公益事業会計及び収益事業会計は特別会計区分が規定されました。
(8)総額主義の原則が規定されました。

4.現代「新社会福祉法人会計基準時代」
平成23(2011)年7月27日現行規定である「社会福祉法人会計基準」が通知され、3年間の猶予期間を経て、平成27年4月1日から適用が義務付けられました。
この基準も通達時期に、実務界では新社会福祉法人会計基準の対応という言葉が使われました。
この時代に、会計基準の統一と法人全体の決算が全ての法人で実現します。
ただし、都道府県や市町村社協など独特の会計が許されている法人は存在します。
引用元:・「社会福祉法人会計基準の制定について」の一部改正について(◆平成27年09月25日雇児発第925001号社援発第925001号老発第925001号)
適用範囲
当時の社会福祉法人は、旧社会福祉法人会計基準、指導指針、就労支援会計処理基準、授産施設会計基準、病院会計準則、訪問看護会計、経理準則、介護老人保健施設会計、企業会計原則と複数の会計基準が適用されていましたが、今回の基準で全ての基準を一元化(串刺し)しました。
特徴
(1)社会福祉事業、公益事業、収益事業の適用範囲を一元化
(2)附属明細書の追加
(3)拠点区分とサービス区分というセグメント会計の考え方の導入
(4)引当金の範囲を徴収不能引当金、賞与引当金、退職給付引当金に限定
(5)1年基準、金融商品の時価会計、リース会計、退職給付会計、減損会計、税効果会計の導入
(6)退職共済制度、共同募金配分金等の取り扱いの明確化
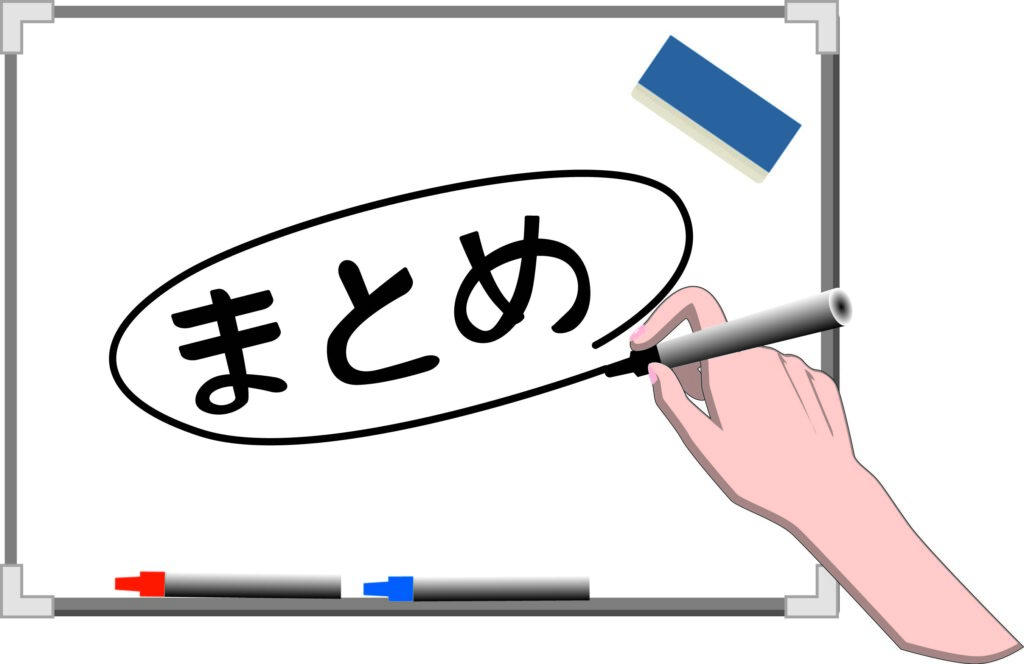
まとめ
社会福祉法人会計の歴史は大きく分けて4つのステージがあります。
(1)昭和28年からの会計要領時代
(2)昭和51年からの経理規程準則時代
(3)平成12年からの社会福祉法人会計基準時代
(4)平成23年からの現行会計基準時代
「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」という有名な言葉があります。
仕事は経験から学ぶ事が基本では?と突っ込みたくなるところですが、自分の経験だけでなく他人の経験にも目を向けた方が知恵の濃度は上がりますし、歴史を学ぶ事でしか得られない、気付きや学びはあるという意味では合っているでしょう。
社会福祉法人は、公費をもらう性質があり、自力で稼ぐ企業会計とは異なる制度的な進化を遂げてきました。
社会福祉法人会計の世界で「利益」という概念は存在しません。なぜなら「利益」という概念は、配当など処分することが前提の言葉で、社会福祉法人は処分することが禁止されているためです。
代わりの概念は「剰余金」です。
社会福祉法人会計の歴史の世界は、いかがでしたでしょうか?
現行基準を身につけながら過去の基準を見返すと、理解の体感が変化していくのが分かります。特に、現在実務を行っている方は「なるほど」という気付きがたくさんあると思います。自分なりに知識の棚卸をしてみることをお勧めします。
当事務所は、社会福祉法人会計基準に関して、法人内の経理担当者向けの教育に関して多くの実績があります。社会福祉法人会計の職員教育は、法人内ではなかなかできません。研修をご希望の法人は、お気軽にご相談下さい。

