社会福祉法人が新会計基準への対応を税理士に任せるメリットは?
制度改正があった時に、対応を税理士に任せるメリットはあります。
もちろん自法人で対応ができるのが理想ですし、実現する法人がある一方、失敗する法人もあります。失敗したデータは簡単には直せませんので、深刻な問題を抱えてしまいます。
仕組みは、最初が肝心。ボタンの掛け違いは避けたいところです。
今回は、任せた時の具体的なメリットを幾つかご紹介します。
目次
簡便法の規定が使える
会計基準には様々な簡便法が用意されています。規定を熟知している税理士は、臨機応変にその法人に合わせて活用してくれます。
制度会計と管理会計の発想を混ぜて並列で一つにしてしまうと、全てを複雑化するしか選択肢がなくなります。
優先順位と取捨選択が重要です。制度会計はシンプルに、必要があれば管理会計で補完する運用ができれば、比較的手間をかけずに、必要な情報が集計できます。

1.就労支援会計編
障害福祉施設の生産活動に係る年間売上高が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、就労支援事業製造原価明細書・就労支援事業販管費明細書に代えて就労支援事業明細書の作成のみで良いことになっています。
また、多種少額の生産活動を行う等の理由により、作業種別ごとに区別することが困難な場合は、作業種別ごとの区分を省略できます。
就労支援会計は社会福祉法人会計の中で最も複雑です。細かく設定して成果の期待できない作業に苦しむのは避けたいところです。
2.公益事業区分編
社会福祉施設と一体的に実施されている小規模な公益事業はその施設の拠点区分に含めて会計処理することができます。
拠点を分けてしまうと貸借対照表も分けなければならないため、仕訳量と難易度が格段に上がります。拠点を細かく分けすぎて、会計処理が追いつかない運用は避けたいところです。
3.収益事業区分編
社会福祉施設等において、会議室を法人が使用しない時期に外部の者に使用させる場合等や専ら施設利用者の利便に供するため売店を経営する場合には、定款に収益事業を記載しなくても良いことになっています。
ただし、社会福祉法上の収益事業と法人税法の収益事業は概念が違いますので、会計と税務をどのように調整するか、事前に設計しておく必要があります。

拠点区分の設定の最適化
社会福祉法人会計の基本単位は拠点です。
独立した拠点を設定しなければならない事業は12個だけです。逆に言えば、それ以外の事業は拠点をまとめてサービス区分として処理することができます。12個以外の小規模な事業を機械的に拠点として独立させてしまうと、いたずらに会計処理が増加します。
拠点を分離してしまうと、その拠点の予算を作成して科目ごとの予実管理をしなければなりません。また、貸借対照表を分けて作成しなければならないため別法人並みに手間が増加します。しかも、一旦非効率な方針を採用してしまうと、その後の施設の開設も非効率な運用を上乗せしていきますので、どこかの時点で業務がパンクしてしまうリスクを抱え続けてしまいます。
拠点の最適化ができていなくて、苦しんでいる法人は比較的多い印象です。
過去の勘定科目体系を整理してくれる
社会福祉法人は企業会計のように自由に勘定科目を使うことはできませんので、会計基準の変更時に勘定科目体系が変わりました。
本来、旧科目から新科目への変換規定を使って、勘定科目体系を一新すべきですが、旧基準の勘定科目を慣れているという理由で、新会計のソフトの中に旧体系を再現してしまう法人があります。
社会福祉法人はたくさんの報告書を作成しますが、想定外の科目についていちいち変換を悩んだり、データのコンバートができなかったりします。また、会計ソフトを変更するときも無駄な手間がかかりますので、負担の少ないオーソドックスな科目体系で経理規定を整備し、会計ソフトに設定したいところです。
同じ取引が、拠点によって違う勘定科目で処理されているのは、よくある指摘事項です。
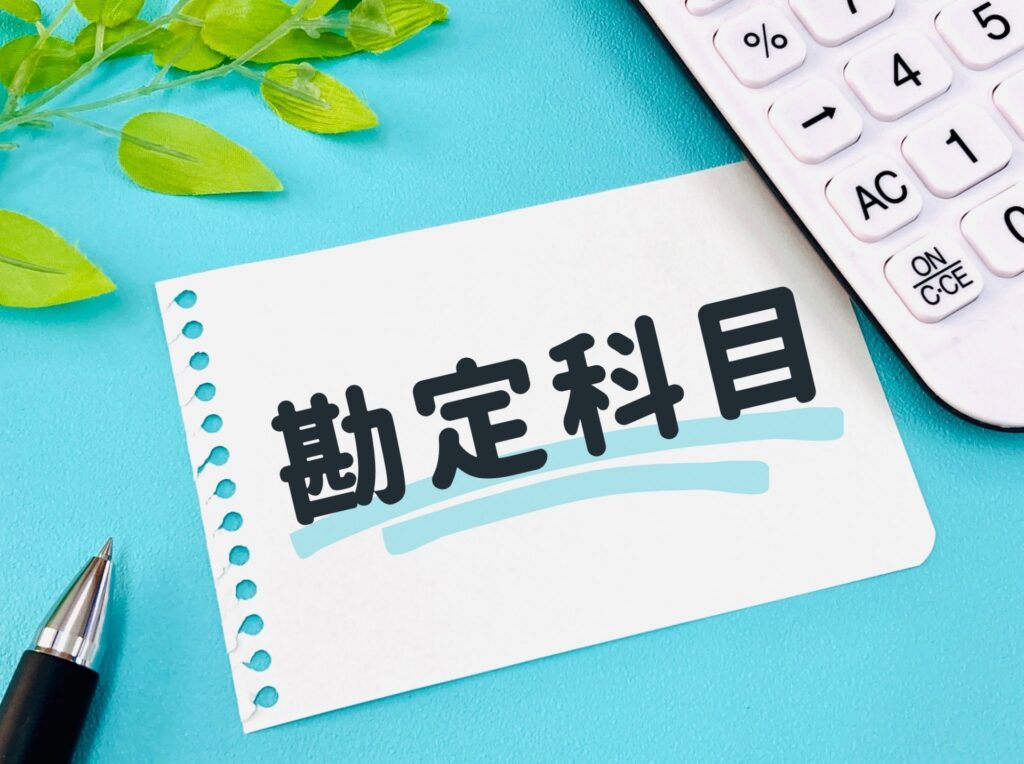
制度上必要のない情報をカットしてくれる
社会福祉法人の決算書の枚数は企業会計と比べると、とても多いです。決算書が数百ページから、大規模な場合は千ページを超えることもになることもあります。
法人全体で必要な書類(情報)と拠点単位で必要な書類(情報)は全く異なります。
拠点の内容によっては、省略可能な帳票もたくさんあります。しかし、必要か不必要かの判断がつかないため、全ての帳票を出力して決算理事会の議案にしてしまう法人があります。作業も紙も無駄なことがほとんどです。制度会計はシンプルに、必要があれば内部向けの管理会計で独自に必要な情報を集計するのが合理的で賢明です。実績のある税理士は、交通整理してくれますので活用しましょう。
いろいろな事情で、必要のない帳票を出力している法人は比較的多い印象です。
費用の配賦を適正化してくれる
費用の配賦は、以下の性質により処理方法が異なります。
(1)拠点を跨ぐ取引(社会福祉事業・公益事業・収益事業)
(2)拠点内で勘定科目を跨ぐ取引(事務費・事業費・原価・販管費)
(3)勘定科目内でサービス区分を跨ぐ取引
(4)勘定科目内で就労支援会計の作業区分を跨ぐ取引
直接費・間接費の考え方、実費弁償・分担金方式の考え方、配賦割合・配賦方法を仕訳で行うか、会計ソフトの機能で機械的に行うか、併用するか…。のやり方が整理されておらず担当者の感覚で処理してしまうと、収益と費用の対応関係が全く分からず、部門単位の経営成績が実態とかけ離れたものになってしまします。
配賦は考え方を誤ると、効果の見込めない手間がいたずらに増加するという特質があります。
実績のある税理士は、制度を守りながら比較的手間のかからない方法を指導してくれます。

まとめ
知見のある税理士を活用することによって、以下の効果が期待できます。
(1)間便法を使って業務効率を上げられます。
(2)会計の基本である拠点を最適化できます。
(3)勘定科目を、規程・会計ソフト・運用の面で整理ができます。
(4)社会福祉法人の鬼門である内部取引や費用の配賦を整理できます。
制度改正を無理矢理に自法人でやってしまった。又は、制度を理解していない税理士に任せてしまったために、とんでもないことになってしまった事例は一定数存在します。
制度はたいていの場合、原則法と簡便法があり、原則法を採用することは制度上問題ありませんが、とても非効率な場合もあります。
更に行う事業によって、年度精算義務や繰入制限など国の通知制限を意識しなければなりません。
一旦、効率の悪い方法を選択してしまうと、非効率を続けざるを得なくなり、直すのにとても労力が要ります。最初が肝心で、制度改正は過去の負の遺産を改善する絶好の機会でもあります。
仕組み作りやデータの構築には時間がかかりますが、壊すのは一瞬です。
決算で分からなくなって、合わすために無理矢理の仕訳を入れたり、不明な勘定科目が貸借対照表に残っていたりしませんか?過去の決算書が間違っているという事例に時々遭遇します。
自法人のやり方が問題ないと自信を持って断言できる法人は素晴らしいですが、もし、不安があるなら、負の遺産の対価を長年払い続けるより、制度を理解していて、実績のある税理士に入ってもらい健全化する方が賢明でしょう。
「今のやり方って効率的なの?」それを自法人で判断するのは難しいです。
現在、何らかの会計的な不安がある法人は、どこに問題があるか?合理化できる可能性はあるか?一度、税理士に診断を依頼して意見を求めてみてはいかがでしょうか?
当事務所は、診断とレポートのスポット対応も可能ですので、不安のある法人は一度ご相談下さい。

