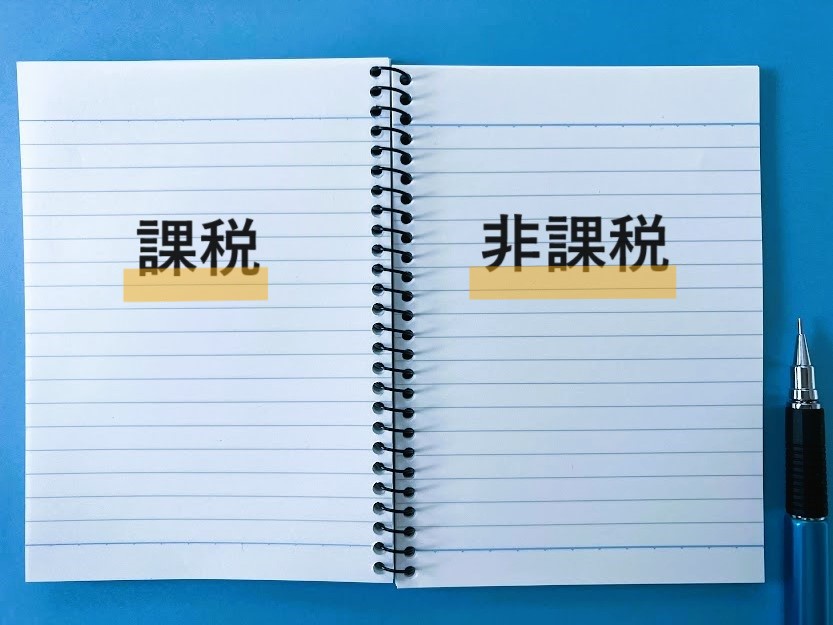社会福祉法人の固定資産税はどこまで免除されるの?
以前、4月12日と4月19日に社会福祉法人の固定資産税の非課税規定の記事を投稿しました。
固定資産税の記事はアクセス数が多いので、お悩みの方が多いことが分かります。
今回は、固定資産税の非課税が及ぶ範囲について考えたいと思います。
解釈になりますので、所轄の自治体や税理士によって見解が分かれる可能性があります。一つの見解としてお読み頂けると幸いです。
目次
社会福祉法人にどんなトラブル事例があるの?
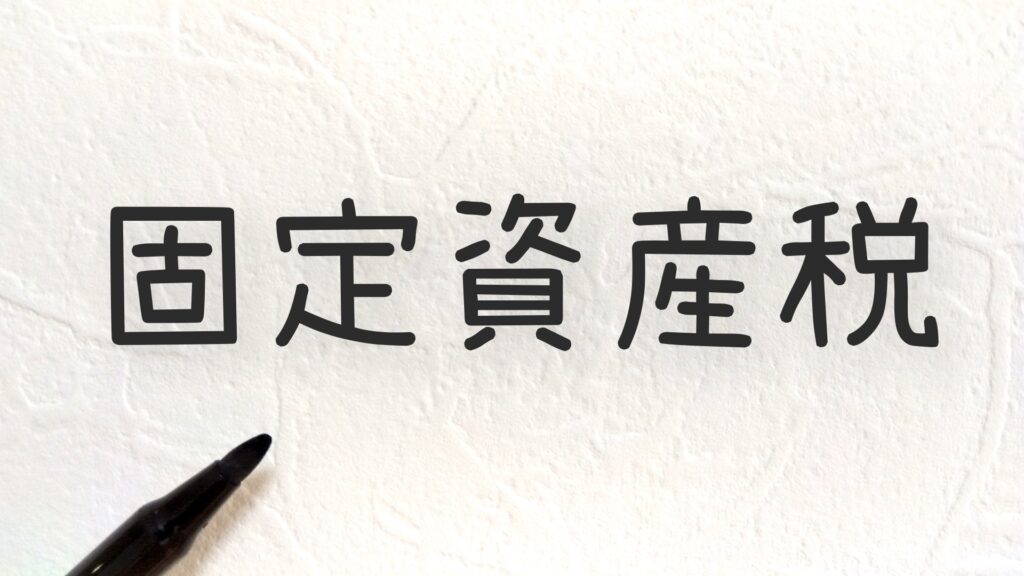
筆者が約20年の間、所属していた社会福祉法人では何度も都税事務所の実地調査を受けましたが、固定資産税に関するトラブルはありませんでした。
税理士になってからは、クライアントによって、時々法人本部の資産が課税されるトラブルがあります。
社会福祉法人の業界で、有名なトラブル事例を一つご紹介します。
東京都大田都税事務所が、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人H会の職員用諸設備に対して「非課税は施設の運営上直接必要な土地・家屋及び償却資産税に限り職員専用部分は該当しない。」として固定資産税賦課処分をしました。H会は東京都を相手に処分の取り消しを求めて提訴し、口頭弁論前に課税処分が取り消され、非課税となったという事例です。
参考:東社協福祉施設経営相談室だより平成18年No50/No.51
社会福祉法人の非課税規定を見ておきましょう!
地方税法348条には「固定資産税は次に掲げる固定資産については課すことができない。」とあります。
一旦課税対象にしてから、非課税や免税にするのではなく、そもそも課税できないという書き方です。
課税できない固定資産は、さらに3つの書き方があります。
(1)直接△△の用に供する固定資産
(2)もっぱら△△の用に供する固定資産
(3)△△の用に供する固定資産
社会福祉法人の固定資産はほとんどすべてが(3)であることが分かります。条件がないということです。
東社協の資料によれば、大田都税事務所の課税処分の理由に「非課税は施設運営に直接必要な資産である」と記載があったようですが、条文的にはそのようになっていません。条文上は直接である必要はありません。

裁判例などの通説
固定資産税の非課税をめぐる紛争は数多くあり、最高裁の判例を含む主要な裁判例での解釈をまとめてみますと、「固定資産税は担税力が無くても資産価値に着目した所有という事実に課税される物税で、非課税規定は政策的な観点から例外的なもので、公平負担の観点からも、非課税規定は文理に即して厳格に解釈されるべき。」という考えが通説のようです。
大田都税事務所は、この厳格にという意味をとても厳しく捉え、職員専用の資産は社会福祉事業に直接は使っていないから課税すべきだと考えたのでしょう。
一つの見解
本部は社会福祉法人にとって、社会福祉法人の制度上必ず設置しなければならない機能ですし、職員用のトイレや更衣室は施設運営に必要と言えます。程度の差はあれ、どこの法人にも当然にある機能です。
もう一度3つの書き方に戻りましょう。
(1)直接特別養護老人ホームの用に供する固定資産
(2)もっぱら特別養護老人ホームの用に供する固定資産
(3)特別養護老人ホームの用に供する固定資産
もし、規定の書き方が1や2であったら、本部や職員用の施設は「直接」でも「もっぱら」でもないために、大田都税事務所のように非課税でないと解釈できる可能性はありますが、3だとしたら特別養護老人ホームの用に供しているのは間違いない事実であるため、非課税でないと解釈するのは無理があるように思います。逆に言うと、特別養護老人ホームの用に「供している」と主張し証明できる納税者に対して、課税庁が「供していない」ことを課税庁側が立証できない限り、課税処分は認められないと解すべきです。
したがって、東京都が課税処分を取り消したのは妥当だと考えます。

まとめ
固定資産税の非課税判定の解釈は、微妙で判断が難しいことはご理解頂けたと思います。
地方税法は、数ある法令の中で一番条文数が多いと言われています。
紛争が多いのも頷けます。
日本国憲法の84条は租税法律主義といわれ、「課税要件明確主義」というものがあり、課税する法律はなるべく一義的で明確でなければならないと理解されています。 また、憲法の14条は公平負担の原則といわれ、同じ条件ならば、同じように公平に課税しなければならないと理解されています。
憲法上の観点からは、読みにくい法律が原因で、固定資産税が同じ条件で課税だったり非課税だったりする実態は望ましくない状態と言えます。
地方税法は条文数が多い上、争点になりそうな箇所がたくさんあります。
万が一トラブルに巻き込まれてしまったら、課税庁の主張を鵜呑みにするのでなく、税理士などの専門家の力を借りることをお勧めします。
当事務所は、課税当局と固定資産税の交渉実績が多数ありますので、お困りの方はお気軽にご相談下さい。