社会福祉法人における消費税で間違えやすい課税対象は?
社会福祉法人の収益の消費税の課税・非課税判定は、非常に難しい領域です。
今回は、一次判定(普通に考えれば)では課税となるが、二次判定(何らかの事情)で非課税となるような「間違えやすい事例」を、障害事業・高齢事業・保育事業分野で、それぞれで代表的なものを紹介します。
目次
社会福祉法人共通事例
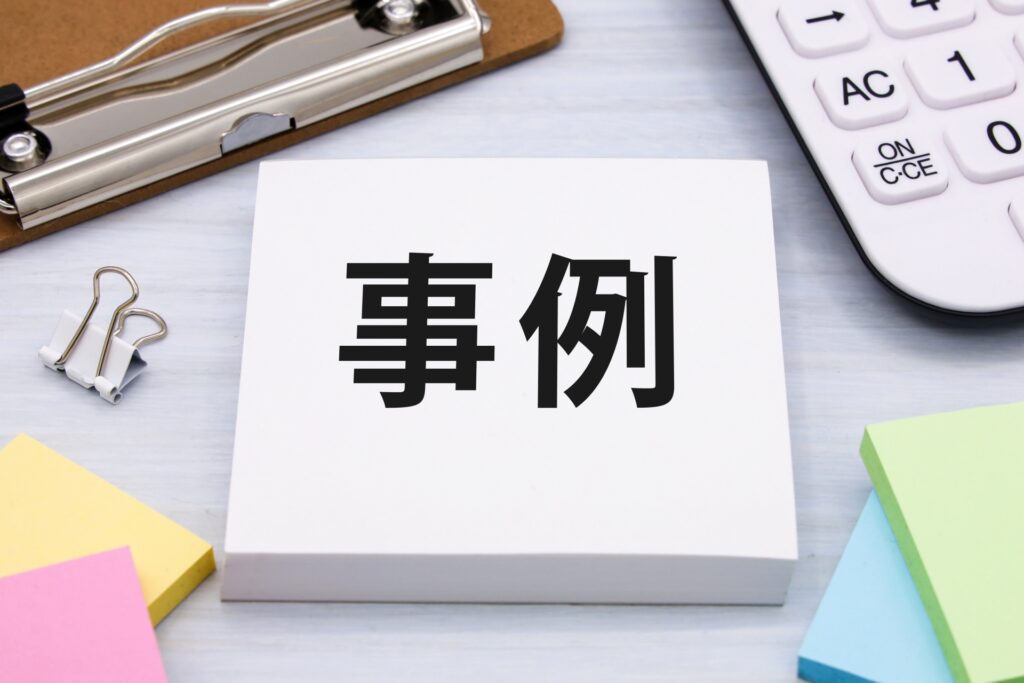
社会福祉法人は自治体などからたくさんの事業の委託を受けていると思います。
受託事業収益は一次判定では、原則的には課税取引となります。ただし、社会福祉法人が非課税に該当する社会福祉事業を丸々受託した場合には、受託事業でない自主事業と同様に考えて非課税となります。
したがって、非課税となるべき社会福祉法上の社会福祉事業以外の事業の受託や、社会福祉事業であっても送迎など切り取った一部の事業の受託は、一次判定のまま課税となるのが原則です。
参考:消費税基本通達6-7-9
障害福祉事業の事例
社会福祉業界で、近年大きな騒動になった相談支援事業の課税判定です。
概要は、いわゆる障害者総合支援法に規定された相談支援事業のうち法5条に規定する一般相談支援事業と特定相談支援事業は非課税だが、法77条に規定する相談支援事業は課税となるのですが、多くの自治体が法77条の事業を非課税と誤認していました。
障害福祉事業の非課税判定は、介護事業が介護保険法を根拠にするように総合支援法を根拠に非課税判定するのでなく社会福祉法を根拠に非課税判定をしますので、上記の3事業は総合支援法を根拠に給付を受ける同類の事業であっても、77条の相談支援事業は社会福祉法の社会福祉事業でないため課税となるという判断です。
一次判定では全て委託事業で課税となりますが、二次判定で法5条に規定する一般相談と特定相談は社会福祉事業として非課税となります。
引用元:障害者相談支援事業に係る社会福祉法上の取扱い等について|厚生労働省

高齢者福祉事業の事例
介護系の社会福祉法人では、有料老人ホームを運営しているケースがあります。
有料老人ホームは社会福祉事業に該当せず公益事業となります。
住宅型有料老人ホームは、介護保険の適用がありませんので、家賃以外のサービスは一次判定の原則どおり課税となります。
特定施設入所者生活介護の指定を受けた介護付き有料老人ホームは、介護保険の適用がありますので、利用料・おむつ代・日常生活費は二次判定により非課税となります。
ただし、日常生活費に関しては特定施設入所者介護に含まれないものと含まれるものがあるのですが、利用者からの徴収区分及び経理上の区分が明確でないとそのすべてが原則に戻り課税として扱われてしまいます。課税・非課税の判定が法人の管理方法にも及ぶという事例です。
児童福祉事業の事例
認可保育園や認定こども園の保育事業収益は社会福祉事業に該当し、二次判定により消費税は非課税となります。
認可外保育施設は法令上、二次判定に進む要因がありませんので、一次判定により課税と考えるのが通常の判定プロセスです。ただし、平成17年以降は社会福祉事業に類する事業として、認可外保育施設指導監督基準を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料については、児童福祉法の規定に基づく認可を受けて設置された保育所の保育料と同様に非課税とされました。したがって、証明書のある認可外保育園は非課税、証明書のない認可外保育園は課税となります。
社会福祉事業でないけれども、類する事業に該当すれば非課税となるものは、類する項目を知らないと二次判定に行けないので、誤解が多いという特徴があります。
引用元:認可外保育施設の利用料|国税庁
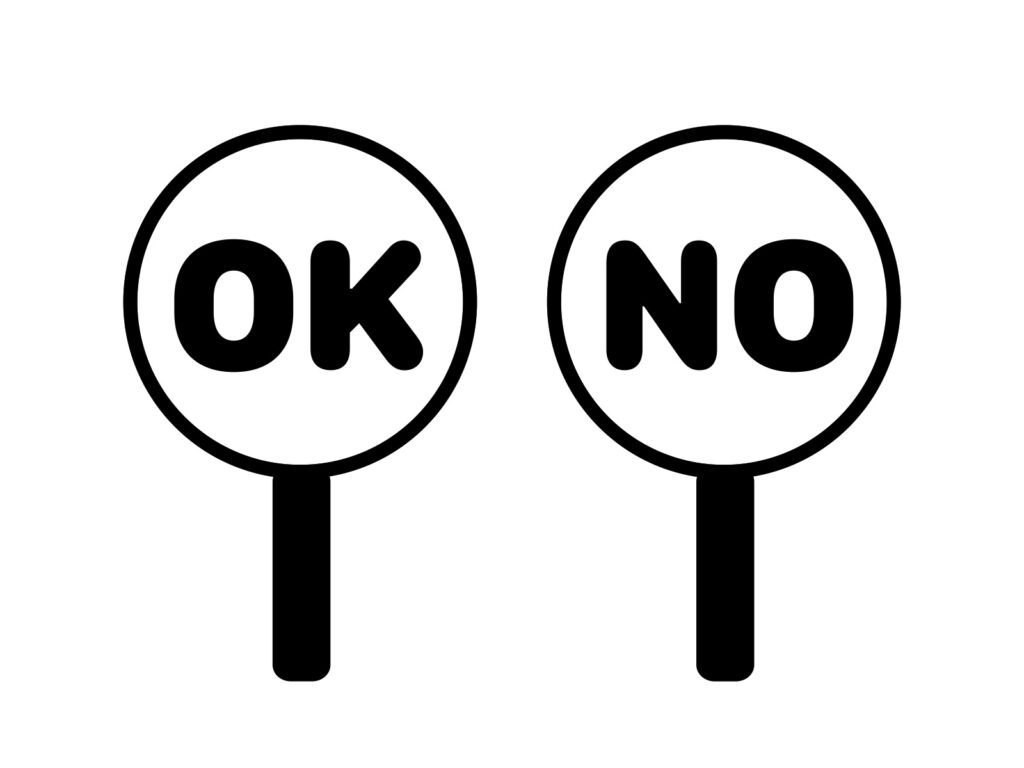
まとめ
金額が大きくなりがちな傾向により、影響が大きくなりそうな4つの判定事例を紹介しました。
(1)自治体から事業を受託した場合の課税判定
(2)障害者相談支援事業の課税判定
(3)有料老人ホームの課税判定
(4)認可外保育園の課税判定
再点検の基準は年間1,000万円を超える取引から順番に行って頂くことをお勧めします。影響額が大きいためです。
拠点数が多い法人は、1拠点では金額が小さいものの全拠点を合計すると1,000万円を超えるような取引もありますので、ご注意ください。
また、本来課税なのに非課税としている場合、税務調査で指摘される可能性が高いので比較的顕在化しやすいですが、本来非課税なのに課税として申告している場合、再点検しないと誰も指摘しないことが多いので、法人がリスクを抱え続けてしまうことがあります。
払わなくてよい税金を払い続けるのも法人のリスクです。
契約書を見ただけでは、判断できないことも多いので、税理士の力を借りて定期的に金額の大きい順番に精査されることをお勧めします。
当事務所は、社会福祉法人の税務に数多くの実績があります。スポットの点検業務も引き受けていますので、顧問業務までは必要ないが、何年かに一度専門家の目を入れたいなどのご要望があれば、お気軽にお問合せ下さい。

