国や地方自治体から委託された社会福祉事業の消費税の扱いは?
前回、社会福祉法人が自治体等から委託事業の消費税の取り扱いについて触れました。
社会福祉法人と自治体等からの委託事業は切っても切り離せません。
委託事業は、業務委託契約や請負契約になりますから、一般的な売上と同じか?という疑問が生じるわけです。
今回は委託事業を受けた場合の実務上の注意点について取り上げたいと思います。
目次
自治体等からの委託事業の実態
自治体等から委託を受けて事業を行っている社会福祉法人は多いです。
国の法令や地方自治体の要綱に基づいて事業を行うものを「自主事業」、委託契約や協定書に基づいて事業を行うものを「指定管理」や「受託事業」などと言葉で使い分けている法人もあります。
2003年に地方自治法が改正になり指定管理制度が広まりました。公立の社会福祉施設も委託できるようになり、いわゆる官立民営施設が増えました。
指定管理の特徴は、議会の承認が必要で複数年契約が基本になります。
一方業務委託契約は、通常の契約プロセスと同様で単年度契約が基本になります。 多くの社会福祉法人で付近の自治体から何らかの受託事業を行っているという実態があります。
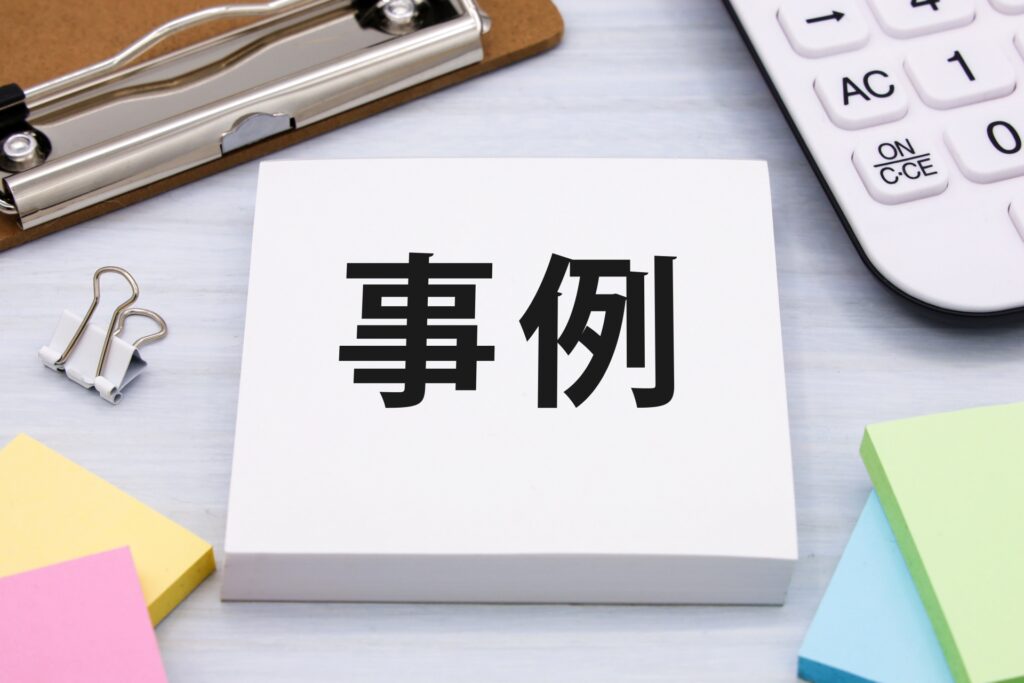
委託事業の範囲と内容
社会福祉法人の指定管理制度の場合は、公立の社会福祉施設を丸ごと引き受ける形が多く、旧来の事業内容や公共設備を継承しながら行いますので、事業の内容は基本的には社会福祉事業か公益事業に該当します。
一方、業務委託契約は、居宅介護事業所や福祉センターのように事業所を丸ごと引き受ける場合もあれば、社会福祉事業の中の送迎サービスや給食サービスだけを引き受ける部分的なものもあります。したがって、事業の内容は社会福祉事業や公益事業の場合もあるし、単なる役務提供の場合もあります。
受託事業の消費税の取り扱い
受託事業は、一次判定では課税となります。しかし、自主事業と同様にその事業が非課税になる規定に該当すれば、二次判定で非課税にできます。
したがって、多くの場合は非課税になりますが、非課税にするためには理由が必要で、この理由探しが複雑で判断が分かれるものが多く、判断が難しいのです。
消費税基本通達6-7-9

実務上の留意点
筆者が所属していた社会福祉法人も自治体からの受託事業や指定管理を行っていましたし、現在のクライアント先も同様に数多くの受託を行っていますので、たくさんの契約書や協定書を見て処理をしてきました。
筆者が長年の実務経験と多くの契約書を精査してきた知見から、特に注意すべき点をまとめます。
必ず契約書が存在します!
受託事業があったら、必ず契約書や協定書がありますので、内容を確認しましょう。
ポイントは、全く同じ事業であっても自治体によって契約書の記載方法や内容が異なる点です。とても細かく事業内容を書いている場合もあるし、あまり細かく書いていない場合もあります。
この契約書から税務判断に必要な情報を読み取るのが基本的な姿勢となります。
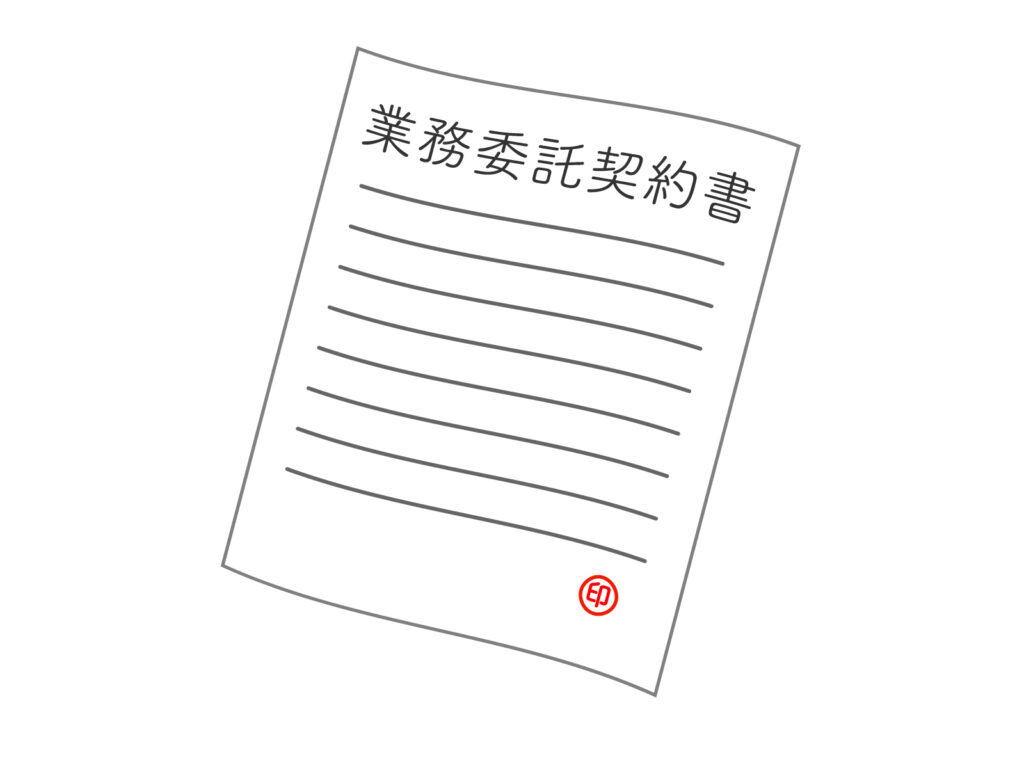
法令上の根拠の記載がない場合がある!
消費税の非課税判定の判断の根拠は、社会福祉法上の社会福祉事業に該当するか否かであったり、介護保険法何条の事業に該当するか否かであったりします。
しかし、契約書をみると〇〇事業とか××事業のように、必ずしも法令上の根拠が明記されていない場合が多いです。
例えば、障害者相談支援事業のような書き方です。
しかし、課税判断は、障害者総合支援法5条の一般相談・特定相談事業は非課税 になり、総合支援法77条の相談支援事業は課税になる。
このように、法令上の根拠と共に判断されますので、法令上の根拠がないと課税判断が正確にはできないことになります。
消費税額の記載が曖昧な場合がある!
これも良く見る問題です。
例えば、〇〇事業、××事業、△△事業の3つの事業を受託していたとします。
契約書に受託金額2億円(税込み)
このように記載されていることがあるのです。 3つの事業の全てが課税なら問題ないのですが、どれか1つの事業が課税でその部分の消費税の可能性もあるのです。
金額の按分も含めて、検討する必要が生じます。
委託先の自治体と認識を合わせる。
大抵の場合、契約書だけでは税務判断ができません。その場合は、クライアントの許可をもらって、委託している自治体にどの部分の消費税を委託料に含めている(想定している)のか?事前に認識のすり合わせをしておくと良いと思います。
ただし、委託している自治体は、所轄の税務署ではありませんので、最終的な税務判断はできません。
判断が難しい場合には、委託している自治体の見解を持参して、税務署に相談する必要があります。税務署に相談する際のポイントは、税務判断に必要な情報(根拠)をきちんと揃えて相談に行くことができるかということになります。
不安がある場合は、税理士に手伝ってもらいましょう。

まとめ
自治体からの委託事業は、一つの取引で金額が大きくなる傾向があります。
社会福祉事業を委託する場合、非課税が多いことから、実は、非課税の事業の中に一部課税事業が混ざっているにも関わらず、契約全体を非課税と考えてしまっているケースが良くあります。
契約書だけを見て判断しようとする姿勢も危険です。なぜなら曖昧な書き方が多いからです。
(1)契約書を確認する。
(2)非課税の根拠を明確にする。
(3)委託先の自治体と認識の擦り合わせをする。
(4)判断が微妙なものは税務署に相談しておく。
金額が大きな契約は、このようなプロセスで確認しておくと良いと思います。
払うべき税金を払わないというリスクと、払わなくて良い税金を払ってしまうリスクもあります。両方のリスクから逃れるためには、正しい税務判断が必要です。
不安がある方は、知見のある税理士に確認作業を手伝ってもらうことをお勧めします。
当事務所は、社会福祉法人の委託契約書を数多く見てきた実績があります。委託に関する税務判断で、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

