社会福祉法人の税務調査で調べられるポイント5つ
社会福祉法人は非課税法人なのに税務調査なんて入るの?
と思われるかもしれませんが、入ることはあります。
申告納税制度である国税に関する税務調査もありますし、賦課課税制度である地方税に関する税務調査もあります。
筆者が23年間のキャリアの中で社会福祉法人の職員としての経験又は税理士として見聞きした社会福祉法人の税務調査についてのポイントを5つご紹介します。
目次
1.税務職員達から見た社会福祉法人

筆者は税務署の職員の経験はありませんが、個人的な繋がりで複数の国税庁のキャリアと言われる元幹部職員や所属税理士会の支部経由で現役税務署の職員に社会福祉法人の税務について質問してきました。税理士は、税理士会を通して現役税務署との意見交換会という機会があり、毎年たくさんの現職税務職員にそれぞれの考えを聞くことができます。
ある幹部経験者は、社会福祉法人の税務は良く分からないし、職員達には苦手意識があるといいます。難しい問題は、国税庁内でもごく一部の人間が判断しているなど、特殊性を強調していました。
また、ある幹部は、社会福祉法人などの公益法人等は「公」の漢字から庁内では「ハム」という隠語があり、福祉に関係する人は、とてもまじめな人々か、逆に悪意のある人々か極端に分かれる傾向があり、真面目にやっている社会福祉法人は基本的に課税する必要が無いが、非課税規定を逆手に取って租税回避や脱税を試みる人たちがいると分かれば必ず潰しに行くと強調していました。たしかに、筆者が税務調査を受けた時に、調査官から「あなた方は真面目過ぎる位真面目ですね。」と言われたことを思い出しました。ただ、その時はたっぷりと課税されましたが…。
総じて、税務署の職員は、非課税の範囲が広く結果的に課税できない法人であるという性質と、規定が特殊で分かりにくいため、あまり積極的に調査に行きたいとは思っていないが、非課税規定を逆手に取り租税回避や脱税を試みる悪意ある人達には「質問検査権を行使して止めさせないといけないと考えている。」という印象があります。
2.源泉所得税の注意点
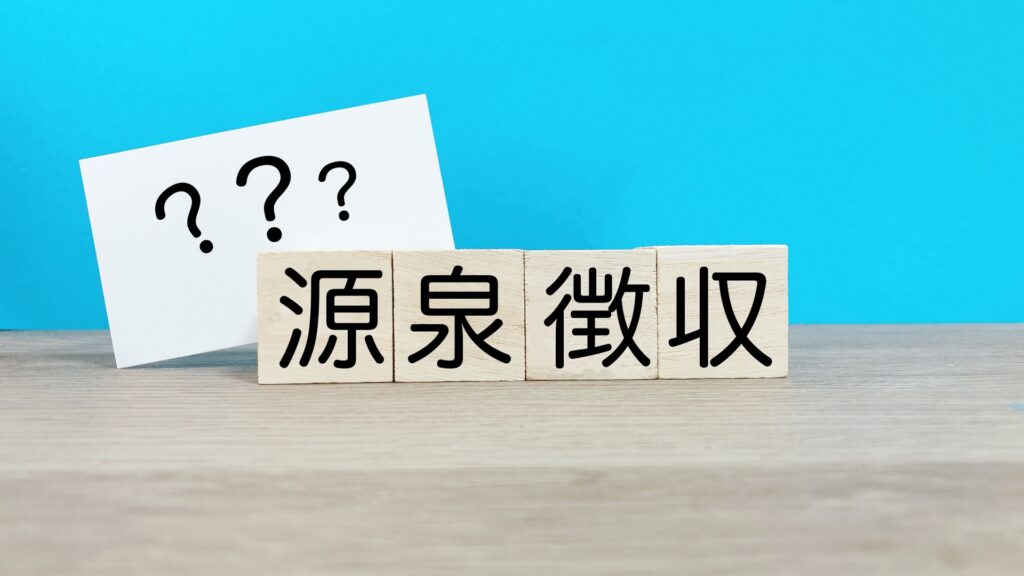
社会福祉法人で給与計算をしていないところはほとんどないため、いくら非課税法人といっても、源泉所得税の納付や年末調整は行います。
社会福祉法人の源泉所得税については、ほぼ株式会社と同じですので、事業者は課税されます。
したがって、定期的に税務調査は入ります。本部で一括納付している場合は本部に、拠点で分散納付している場合は拠点に入ります。
今回は2つ間違えやすい事例を紹介します。
嘱託医に支払う報酬
社会福祉法人は営む事業の認可の影響で、近所の医師と嘱託医の契約をしている法人が多いと思います。
医療法人等の法人と契約している場合は源泉の必要はありませんが、開業医個人と契約している場合は源泉が必要です。
不思議な感じですが、委託する社会福祉法人に医師に対する指揮命令権がないにも関わらず、嘱託医の報酬は税法の世界だけ「給与」として扱われ、消費税も課税されません。
同じ士業でも、弁護士や税理士に対する報酬は、もちろん報酬で消費税も課税取引ですので、例外的な取り扱いのため、間違いやすい事例となります。
外部の役員に対する報酬
社会福祉法人の場合、役員の報酬は役員報酬規程に定めますが、評議員などの外部の役員の報酬体系が1回の会議の参加につき20,000円などとなっている場合があります。
これを何故か報酬(謝金)として考え、10.21%の源泉税を差し引き、毎回17,958円を手渡ししている法人がありますが、こちらも報酬でなく給与として扱うべきです。 したがって、一般の社員と同様に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与の支給方法に応じ、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って源泉税額を求めるべきということになります。
筆者も何度か税務調査で指摘された経験があります。
3.法人税法の注意点
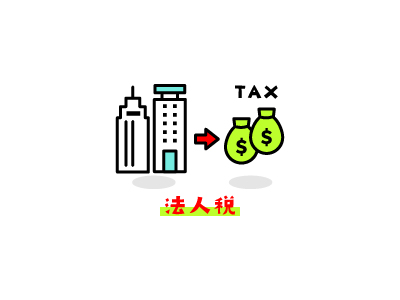
社会福祉法人は法人税法上の収益事業を行う場合に限り法人税を納める義務があります。
収益事業を行う法人で、社会福祉法上の収益事業と法人税法上の収益事業の概念が完全に一致している法人は問題になりませんが、一致していない場合は税務調査で問題になることがあります。
もし、問題になった場合は、知見のある税理士でないと対応できないと思います。 今回は少しだけ争点を取り上げますが、税務署に対抗するには全く不十分です。
基本通達15-1-1問題
法人税基本通達15-1-1に、「公益法人等が収益事業の範囲に掲げる34事業のいずれかに該当する事業を行う場合には、たとえその行う事業がその公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、その事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。」とあります。
社会福祉法人は、社会福祉事業であっても34事業のいずれかに該当する場合は、法人税が課税されると読めるように思いますが、学者間でも見解が分かれています。
国税庁は、保育園や認定こども園は「育児サービス業」として34事業に該当しないと公式見解が出されていますが、障害福祉事業は「請負業」か「医療保健業」として34事業に該当すると解釈されています。理論的に整合していない解釈のため実務界から批判が多い論点です。
34事業の該当性は最高裁の判例を含めて、非常に厄介です。
請負業問題
この論点も学者間や実務界で批判が多いところです。
収益事業の34事業の中に請負業があり、請負業を広くとらえると、ほとんどの事業が請負業として課税できてしまうからです。
戦後まもなくの収益事業を開始した時点の立法趣旨は、イコールフッティングを目的として、営業税の課税科目から展開したものなので、原則非課税の法人を限定的に課税すべき立法趣旨から、技芸教授業のように限定的に解釈されるべきであると思われますが、最近の裁判例では民法の概念を借用し広く捉えられている印象です。
もし、課税当局に請負業を広く解釈して、持ち出されるとほとんどの社会福祉事業が課税できる可能性が出てしまいます。こちらの論点も厄介です。
付随行為問題
収益事業の範囲は施行令5条にありますが、その括弧書きに次の文言があります。
(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)
収益事業に付随して行われる行為が、たとえ非課税なものであっても、収益事業に含まれると解釈する方が一定数いて、障害福祉サービス事業の訓練等給付費収益は請負業で、生産活動部分は付随行為で、収益全体が請負業であると解釈した国税不服審判の裁決例が存在します。
こちらも学者間で批判が多い論点で、付随行為か単独行為かは、明文から文理解釈できないので解釈になりますが、範囲設定が非課税事業を課税事業に変えてしまいますので、非常に厄介な論点です。
4.消費税法の注意点

消費税の税務調査は、売上が良く確認されます。理由とすると、売上の多寡が、税額に影響するばかりでなく、納税義務があるか否か?簡易課税制度が使えるか否かなど構造的に影響するためです。
社会福祉法人は、基本的には非課税売上が多いからといって、盲目的に非課税にしてしまうのは危険です。
税務調査では、取引毎にこれは何故非課税売上なのですか?と順番に聞いてきますので、〇〇なので非課税ですと答えられるようにしておけば問題ありません。
5.固定資産税の注意点

固定資産税の調査もあります。
税務署の職員ではありませんが、地方自治体の職員が現地に来て、現物を確認することもしばしばです。
例えば、保育園の「職員休憩室」というプレートの部屋を見て、これは休憩目的の部屋で社会福祉事業に使用していないのでは?と聞いてきたりします。
「はい」と答えると、その瞬間に課税となります。
「いいえ」社会福祉事業の用に使っていると説明して理解してくれる調査官もいますが、理解しない調査官もいます。
誤解されないように、部屋プレートを例えば「保育準備室」などの名称にして明らかに社会福祉事業の用に使っているという事を明示した方が課税されるリスクは減少すると思います。
まとめ

非課税法人と言われる社会福祉法人といえども、税務調査は入ります。
(1)税務署の社会福祉法人への関心は高くありません。真面目に正しく処理していれば全く怖くありません。非課税規定を悪用した租税回避や脱税の試みは税務職員の正義感をとても刺激します。
(2)所得税は、給与と報酬を正しく源泉しましょう。源泉漏れを後から本人より徴収(精算)するのは実務的に極めて困難です。
(3)法人税は、非常に厄介です。もし調査が入ったら、知見のある税理士に手伝ってもらって下さい。
(4)消費税は、売上が良く聞かれます。非課税になる理由を把握しておきましょう。
(5)固定資産税は、貼りだされた現物のネーミングが誤解されないようにしましょう。
税務調査の案内が来たら、次の事を意識すると良いと思います。
・調査の時期→7月から9月の税務署の年度初めの調査は注意が必要
・調査の期間→長ければ長いほど注意が必要
・調査に来る職員の数→多ければ多いほど注意が必要
・調査官の役職や部署→特殊な部署の同行やグレードが高ければ高いほど注意が必要(税理士なら名簿を持っていますので全ての税務職員の情報を把握できます。)
事前の日程調整の際に、もし注意しなければならない項目があると、内部通報(いわゆるタレコミの類)などこちらに不利な情報が当局に渡っている可能性がありえますので、知見のある税理士や弁護士の立ち合いを検討することをお勧めします。
当事務所は、税務署の税務調査だけでなく、固定資産税の調査の立ち合いの実績も数多くあります。税務調査でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

