社会福祉法人の社宅や社員寮の固定資産税も非課税?
社会福祉法人の社宅の固定資産税については、時々質問を受けますが、税理士にとっては敗戦濃厚な論点です。
社会福祉法人の方々にとっては、敗戦濃厚な固定資産と逆転勝利ができる固定資産の見極めと理由が重要となります。仕組みを知り、逆転率が高い資産に時間を割きコストが減らせる可能性が高まるからです。
今回は、社会福祉法人の社宅制度について深堀します。
目次
社会福祉法人と社宅制度
社会福祉法人は公費を受け入れる特徴がありますので、福利厚生色が強い社宅制度なんてあるの?と疑問を持つ方もいらっしゃると思いますが、あります。
歴史的には、戦後間もない昭和時代に自宅の一部を寄付して立ち上げた社会福祉法人などは、役員や職員が施設の中で生活していた実態が普通にありましたし、保育士の宿舎借り上げ補助金制度は2015(平成27)年から始まり、近年では高齢者施設や障害福祉施設の宿舎借り上げ補助制度も整備されたことから、社宅制度を採用している社会福祉法人は多数あります。
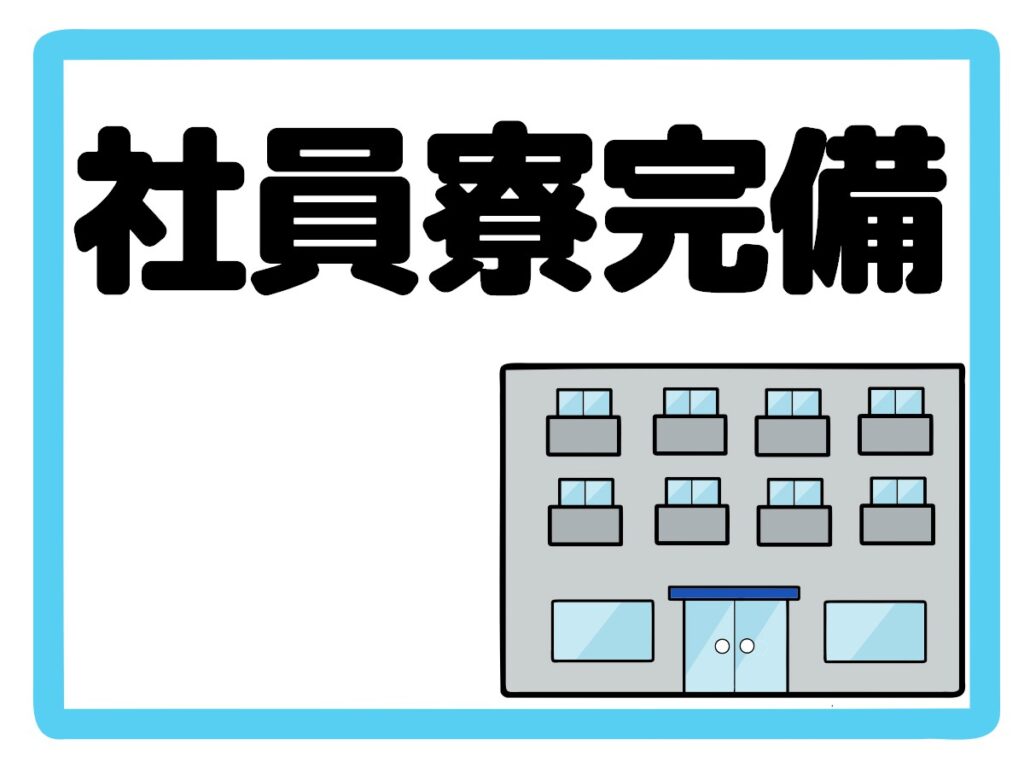
社会福祉法人の社宅制度と所得税
社宅制度を採用した社会福祉法人にとって最初の悩み事は、社宅規程に自己負担をさせるべきかという方針の決定です。福利厚生色の強い支出となりますので、規程の整備は補助を申請する上でも指導検査対策でも必須となります。
所得税法上は、自己負担が無い場合は、家賃相当額が給与として課税されてしまいます。職員から見るとお金が1円も増えないのに税金でお金が減りますので、納得ができない方もいると思います。例えば、法人所有の車両を法人の許可をもらって無料で借りて転勤の引っ越しをしたら、車代相当額が課税されたとなると納得感はないですね。
社宅制度について、国は基本的な考え方として、業務上の福利厚生費ではなく、「家賃は個人が負担すべきもの」で法人から個人への経済的な利益の供与と考えていることが分かります。
ただし、家賃相当額の50%(家賃額ではない*)以上を本人に負担させていれば、給与として課税されません。国は、規定額の半分以上を負担していれば、補助率は50%以下になりますので自己負担の原則が満たされると考えていることがわかります。簡単に言うと、法人の補助が半分以下ならば福利厚生費として認めますよ=源泉しなくて良いですよということになります。
*税務上の「賃貸料相当額」は複雑な計算式(固定資産税の課税標準額などを使用)に基づきます。
結果的に、職員にとっては、自己負担額を法人に払うか、所得税を国に払うかいずれかの負担が強いられているという構図になります。
一方、法人側は、宿舎借り上げ補助金を申請しているか否かが判断の分かれ目になります。自己負担分は、原則として補助金の申請ができないため、限度額まで申請額を増やすためには自己負担をさせない方が補助金の申請額としては有利な場合が多いためです。
宿舎借り上げ補助金を申請する場合は、上限の限度額まで申請して、本人負担をさせずに、給与計算上で加算と減算を同時に行い、源泉する方が本人と法人に得だと考える法人が比較的多い印象です。理由は家賃相当額の50%にかかる税金の方が低いことが多いため、結果的に本人の持ち出しが少ないと考えるためです。
参考元:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
社会福祉法人と宿舎借り上げ補助制度
宿舎借り上げ補助制度を活用して社宅規程を設ける法人は多くありますが、宿舎借り上げ制度は読んで字の如く、法人がお部屋を法人名義で不動産所有者から賃貸して、それを従業員に使わせる場合の補助金ですので、原則として自社物件に対する補助申請はできません。
したがって、現在の社宅制度は、ほとんどが賃貸物件で、自社物件を社宅にしている法人は稀です。社宅物件=ほぼ賃貸物件という構造は、そのような理由です。
社宅物件と固定資産税

固定資産税は、賃貸物件には課税されません。所有者に課税されており、借りている社会福祉法人には課税されないという意味です。
借りている社会福祉法人も実質的には負担しているのでは?という反論が予想できます。確かに、社会福祉法人が支払う賃料の中に固定資産税相当額が入っていますが、社宅補助金制度の補助金で賄える場合は、実質的にも負担していません。
そういう事情がありますので、社会福祉法人の社宅で固定資産税が課税される例は極めて稀なケースであるという事がお分かり頂けたと思います。
ただ、自社物件に関しては課税される可能性が高いです。
逆転劇例について、例えば、社会福祉施設内に空き部屋があったとしましょう。空き部屋は社会福祉事業の用に使っていませんので、課税されます。しかし、単なる空き部屋ではなく、おむつ等の備品保管庫として『社会福祉事業の用に供している』実態を証明できれば、非課税が認められる可能性があります。定められた社会福祉事業にその部屋を使用しているからです。
一方、完全なプライベート空間である社宅は、どのように考えても社会福祉事業の用に使うということができないことになります。これが、敗戦濃厚な理由となります。 ただ、社宅であっても、もし社会福祉事業の用に使っていることが証明できれば、非課税になりますが、証明が最も難しい資産の一つとお考え下さい。
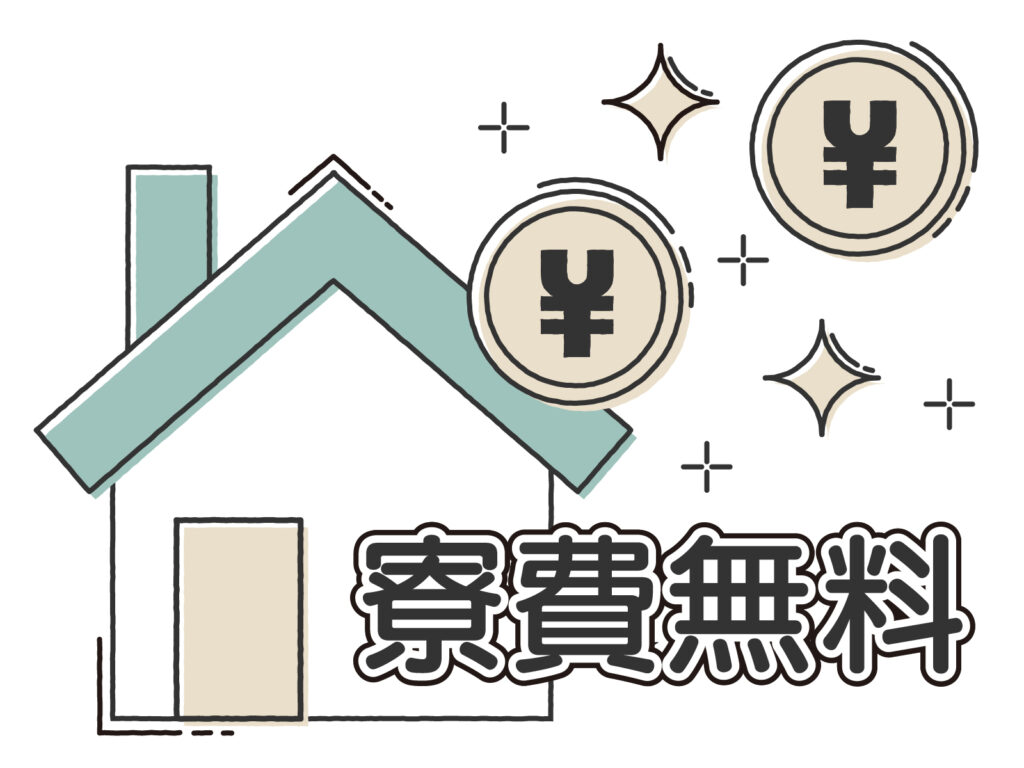
まとめ
社会福祉法人と社宅制度について深堀しました。
(1)社宅制度を採用している社会福祉法人は昔も今もたくさんあります。
(2)社宅費用は、本人負担の原則から、家賃相当額(家賃額でない)の50%以上の自己負担がないと給与課税されます。
(3)社会福祉業界は、宿舎借り上げ補助金制度が充実しており、賃貸物件により社宅を確保している社会福祉法人がほとんどである。
(4)社宅物件は、自社物件にしか固定資産税は課税されないが、プライベート空間であるため、社会福祉事業の用に使うという非課税の要件が満たされにくい。
宿舎借り上げ補助金を活用して、社宅制度を採用するのはとても賢明な判断だと思います。職員から見て、より魅力的な法人になり、有利な採用活動を続けるためには、自己負担額の設定や課税関係の説明が重要です。
そのためには、法人が補助金制度や税制を正しく理解して、優れた社宅規程を作成することが重要です。社宅制度は職員と信頼関係を構築するための重要なツールです。
間違えても、ルーズな管理で各人の自己負担部分が分からないとか、自己負担部分の回収ができていない退職者がたくさんいるとかにならないようにして下さい。職員との信頼関係が壊れ離職率が上がる原因になります。
当事務所は、社宅制度の整理の経験があります。万が一、管理がどうにもならなくなってしまった場合は、スポット契約で税理士の力を借りて整理することをご検討のうえご相談下さい。

