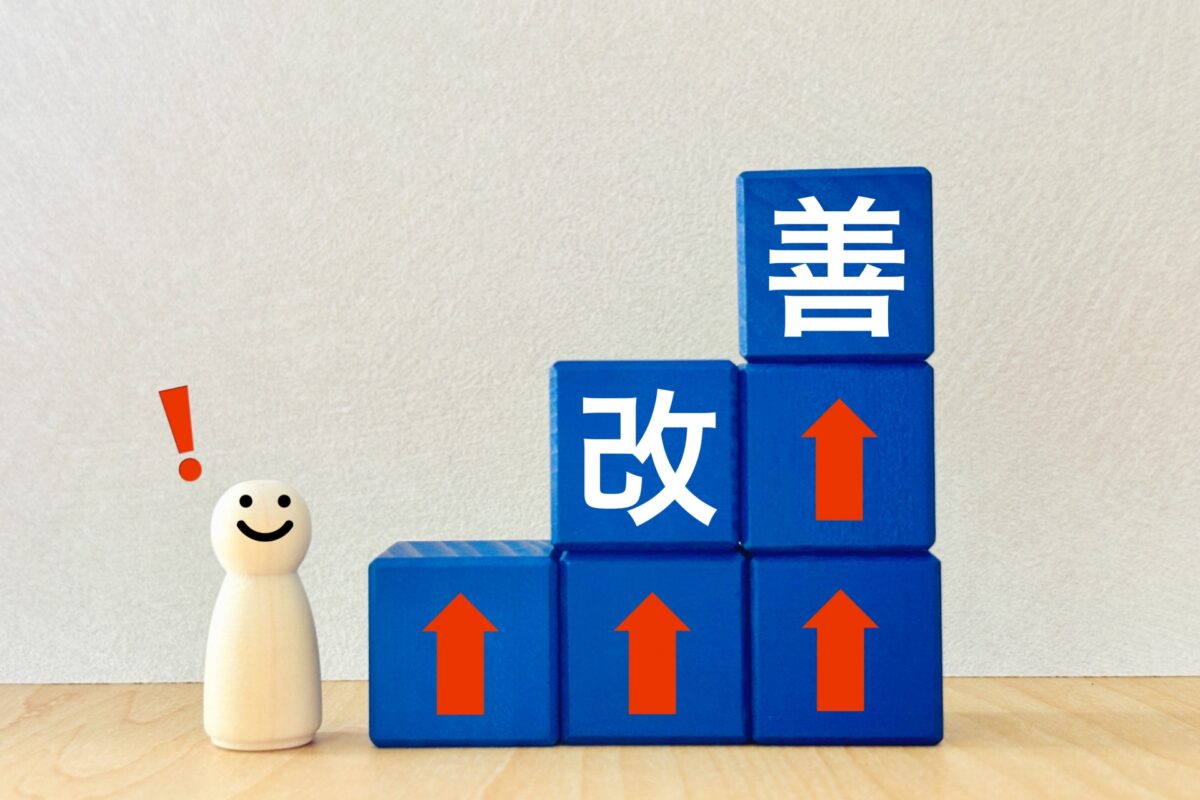社会福祉法人の経営改善を税理士に相談するメリット
社会福祉法人が経営改善を行う必要が生じた時に、税理士に相談するメリットはいくつもございます。
今回は、社会福祉法人専門の税理士である立花がその沢山のメリットと注意するべきポイントも併せて紹介いたします。
まず、メリットを紹介する前に、最近、社会福祉法人の経営改善を行う営業広告を見かけませんか?個人的には注意が必要だという意見です。
理由は、筆者が現役の社会福祉法人の管理職時代に経営改善がとっても大変だった経験に比べ、税理士になってからは比較的簡単に経営改善のアドバイスができてしまうからです。見るとやるとは大違いなのです。
目次
経営診断の捉え方
社会福祉法人に限らず、経営改善は経営診断を前提にして行うことが多いです。
経営診断は健康診断によく似ていますので、健康診断を参考に、筆者が経営改善をどのように捉えているかから始めます。
「バカの壁」で有名な元東京大学医学部教授の養老孟司先生は、取材記事やご本人のYouTubeで、ご本人は健康診断を受けない方針で、「健康診断を受けた人と受けない人の死亡率に差がない」という研究結果があり、切り取った検査結果だけで健康を判断することは危険で、むしろ身体に向き合う事の重要性を説きます。また、医師との関係性は医師の能力だけでなく相性を優先すべきだと言います。
経営診断も同様に経営の健全化や持続可能性に有効であるという科学的なデータはありません。
確かに、経営診断結果は説得力があり、実績同様に絶対的な事実だという危険な風潮はあるように思います。そのような数値至上主義に傾かないためにも、「経営改善業務は、平均値から外れた数値の平準化が仕事なのでなく、その法人に向き合い、例えば、従業員同士の風通しの悪さなど数値に現れない痛みに向き合い、その法人の持続可能性を最大化するのが仕事である。」というのが筆者の意見です。
数値を平均化することが目的ではないのです。
次項からメリットのご紹介です。

メリット1:税理士の性質が分かる
税理士の1つの特徴として、たくさんのクライアントに接しているということが言えます。
社会福祉法人専門でしたら、他の社会福祉法人のやり方を知っているでしょうし、福祉業界専門でしたら、株式会社など営利法人で社会福祉事業を行っているやり方を知っていますので、社会福祉法人の中にいると必ず感じる「他の法人はどうやっているのだろう?」という疑問に答えられることが挙げられます。
また、経営改善は収益獲得の努力か費用削減の努力の二方向しかありませんので、経営改善を相談した時に、どちらの方向性を言い、どこを注視しているかによって、その税理士が経営の観点で重視している姿勢が分かります。
例えば、社会福祉法人の「経営改善は分からない」とか「そういう事はアドバイスできない」という税理士も当然いますので、それもその税理士の特徴ということになります。
会計や税務の質問は、制度上の根拠があり、どの税理士でもほとんど似たようなことを言う傾向がありますが経営相談は違います。税理士の特徴の把握や、税理士との相性を測るための投げかけとしては、とても良い相談項目と言えます。
メリット2:客観的で中立な意見が手に入る
「経営者は人件費総額が安い方が嬉しいし、従業員は給料が高い方が嬉しい。」
「売り手は商品が高く売れる方が良いし、買い手は安く買える方が良い。」
どちらの意見も正しいため、当たり前のことですが、どちらか一方方向に進むことは許されず、経営改善は、利害が対立する要素をいかにして折り合いをつけるかという、相容れない大変な作業となります。
悪く言えば妥協ですので、両者が納得しないケースも多々生じ得ます。
法人内で、経営改善を進める場合、当事者同士の話し合いは、特定の立場の利益代弁になりがちで、仕方のないことですが、冷静さを欠くことがあります。
声の大きい人の意見が通りやすいという傾向はどこの法人にもあります。
税理士は法人内の当事者でもないですし、特定の立場の利益代弁をする必要もありません。また、他の法人の例も知っていますので、相談して頂ければ客観的で冷静な意見を提供することができます。

メリット3:税理士はいち早く情報を持っている
記帳代行や月次のチェックを税理士に委託している場合、月次の経営情報をいち早く知っているのは税理士です。同様に、決算整理や税務申告を依頼している場合も、決算の経営情報をいち早く知っているのも税理士です。
経営の改善をする場合、如何に早く情報を収集して行動するかのスピード勝負ということが良くあります。
作業している税理士は、その法人の変化にいち早く気が付きます。
また、その法人の経理情報を知っていますので、動きを予測することもある程度できます。
他にも、最新の会計や税務の制度をよく知っているなど、税理士を活用するメリットはたくさんあります。
メリット4:税理士は精神的支柱になりうる
経営者は元気な方が多いですが、重圧もあり孤独な職種でもあります。
同族系の社会福祉法人の経営者は、同族があって組織があるのでなく、組織があって我々があるので、実力を付けないと体制が維持できないという話も聞きますし、現場上がりの理事長は、経営者の立場でなく現場の立場で経営をしてしまうため、経営改善が進まないという話も聞きます。
また、機微な情報は、法人内の誰にでも相談できる訳ではありません。話したくても話せないことはたくさんあるというのは経営者からよく聞きます。
経営者といえども人の子ですから、機微な情報であっても、誰かに話したいとか誰かの意見を聞きたいという気持ちは理解できますし、経営コンサルや、外部のコミュニティに共感や癒しを求める方が多いのも頷けます。
税理士は、定期的かつ長期な付き合いになりますし、税理士法で品質が担保されている税理士に相談できるのであればコストの面でも、情報漏洩の面でも望ましいと思います。
そのためにも、経営者が本当に信用できる税理士を選んで契約することが大切になると思います。税理士を活用するのは一石二鳥が手に入る潜在的なお宝ツールと言えます。

まとめ
税理士は、提出された資料に基づき処理をする事後処理部隊ですので、前のめりに経営に口出しするのは望ましくないという考えもありますが、最も身近な税理士を上手に活用して経営改善を進めるべきという考え方もあります。
(1)税理士を経営改善に巻き込むことによって税理士の性質がより理解できる。
(2)税理士は当事者にはできない、中立で客観的な意見が言える。
(3)税理士はその法人の経営改善に必要な情報をいち早く持っている。
(4)税理士法で品質が保証されている税理士は、長い付き合いとなり精神的な支柱になりうる。
社会福祉法人の約4割が赤字といわれ、経営を改善するのは至難の業です。
筆者も言われる側の苦しみと、言う側の苦しみを経験しましたが、経営改善は立場の違いによる正義と正義がぶつかるため、一方方向に進まず、停滞してしまう傾向があります。
経営改善を誰かにお任せや丸投げでやってもらうとか、法人内で数名の狭い範囲で改善を完成させようという姿勢でなく、税理士を活用して広くコンセンサスを得て、たくさんの人に協力してもらいながら経営改善を進めていくという姿勢の方が成功率は高いと思います。
経営改善の最初の関門は、法人内のリーダーシップと風通しの良さだと思いますので、参考にして頂けると幸いです。
当事務所は、無料相談も引き受けていますし、定期的なボランティア活動も実施しております。社会福祉法人の経営について、ご不安ございましたらお気軽にお声掛けください。