社会福祉法人は経営改善セミナーを受けた方が良い?
もし、筆者が社会福祉法人は経営改善セミナーを受けた方が良いか聞かれたら、「受けた方が良いです」と答えます。
例えば、税理士試験の業界では、受験生に対し、「合格体験記や過去問を研究して、自分に合った勉強法を確立するのが合格のコツです。」と説明しています。経験者として全く同感です。
経営改善のコツは、セミナーや書籍から情報を研究して、自法人に合ったアクションプランを立て効果との因果関係を把握することです。経験者として全く同感です。
筆者も社会福祉法人向けセミナー講師の経験がありますので、今回は、セミナーの活用術についてご紹介します。
目次
社会福祉法人向けセミナーの特徴
星の数ほどあるセミナーはその種類により、取得できる情報は全く異なります。
逆に言えば、皆さんは欲しい情報によってセミナーを選ぶ必要があるということになります。
以下で、意識した方がよいセミナーの種類をご案内します。
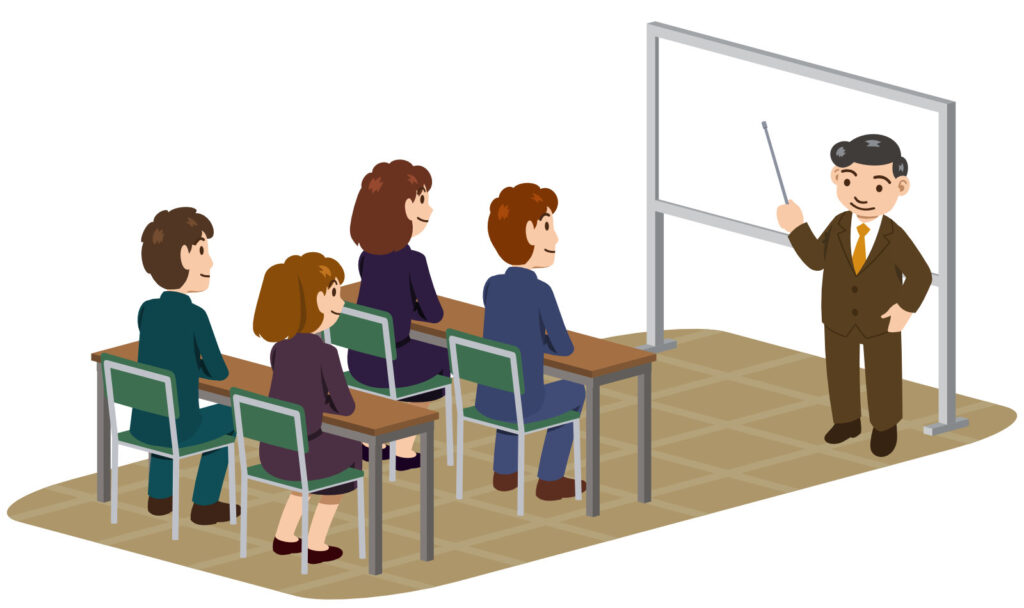
1.社会福祉法人向け無料セミナー
無料セミナーのメリットは受講料がかからないことですが、一般的に言われているデメリット以外にも、注意すべき点があります。。
一般的に、無料セミナーは講師の質が低いのではないかと思われるかもしれませんが、講師の質は有料セミナーとほとんど変わらないです。
一般的なデメリットとして、セミナー自体にフック(仕掛け)がかかっており、個人情報が収集されたり、商材を売り込まれたりという心配が言われますが、こちらも皆さん十分に承知されていて上手に対応できています。無料の範囲で活用するという強い意志を持たれています。
無料セミナーの最大のデメリットは、テーマがスポンサーに寄せられていて、スポンサーの利益になるように、講師が話せる内容に制限があることです。量的にも質的にも、講師から見た最大の利益のベクトルが受講者でなくスポンサーに向いていることです。
2.社会福祉法人向け有料セミナー
有料セミナーのデメリットは、受講料が高いことです。採算を合わせようとするとかなりの金額になるはずです。
傾向として、大学の教授や省庁の幹部などを招聘する有識者系と、社会福祉法人の現職の理事や社会福祉法人に特化した税理士などを招聘する実務者系に分かれると思います。有識者はマクロ系のお話が多く、実務者系はミクロ系のお話が多いです。同じテーマでも全く異なる話をしますので、欲しい情報によって選択する必要があります。
選択するための指針は次項の目的意識が必要です。
社会福祉法人の経営改善は目的意識が大切
経営改善といっても、何をどうやって改善するのか?雲をつかむような話になります。
そこで大切なのは、受講者の目付です。ここで言う目付とは、日常業務の中での欲しいものの予想で、例えば、もう少し職員に給料を払って、職員採用を有利に進めたいが、払えるお金が不足しているとか、利用者が定員割れしていて無駄がある現状を何とかしたいといった問題意識から生じた将来の願望です。
例えば、ホームページで集客するという目標なら、必ずしも社会福祉法人向けのセミナーである必要はないかもしれません。
この将来の願望は、強ければ強いほど、成功率は高まると言えます。セミナーを受講する前に行って頂きたい作業は、この目付の作業です。目付ができれば、参加すべきセミナーの取捨選択がやりやすくなります。

社会福祉法人向けセミナーから情報を取りに行くという意識
セミナーで入手すべき情報は「その手があったか!」という気付きです。
受け身的な姿勢で、少子高齢化や国の財源などマクロ経済の分析結果を見せられて分かった気になっていませんか?実務家の目的は、知識を得ること自体ではなく、それを現場でどう活かすかにあります。
セミナー講師で有名な税理士の先輩は、自分も色々なセミナーに今でも参加するが、印象に残る言葉や心に刺さるキーワードは、一つあるかどうかだ。でも、その一つの積み重ねが自分の引き出しを増やし、スキルの成長に欠かせないと言っていました。 そこで今回は、心に刺さりやすくなる2つの方向性をご紹介します。
1.社会福祉法の制度上の視点
例えば、社会福祉法人で資金繰りを改善して借入額や利息の支払いを減らしたいという目付を持ったとしましょう。銀行は通常社会福祉法人の制度に精通していませんから、本部に資金を集めろとか、拠点間で繰入をして返済原資に回せとか言うことがありますが、制度上自由な資金移動は許容されません。
指導検査では、銀行から言われたので、仕方なく資金移動しましたと主張しても通用しません。
もし、認可保育園の弾力運用通知など資金規制を守りながら改善したいならば、必ず制度を理解する必要があります。
セミナーと通じて、その制度の理解と、その制度を上手に運用している事例の情報を入手しましょう。

2.アクションプランに対する因果関係
例えば、社会福祉法人は、職員の施設(拠点)への帰属意識が強い傾向にあります。歴史的な背景や制度上の必要性からその傾向は、昔から変わりません。他の施設は、ほとんど別の法人だと思うくらい、接点がない法人も多いです。
帰属意識が強すぎると、管理部門が管理し難くなるとか、施設内の風通しが悪くなり離職率が上がるなどの弊害があり、問題意識を持つ経営者が多いです。
このような目付を持った時に、入手したい情報はアクションプランとその因果関係の評価です。
この論点に対して、筆者がセミナーで聞いたことがある二つの取り組み事例を紹介します。
一つ目は、A施設(拠点)とB施設(拠点)の管理職を総入れ替えしたという事例です。 この理事長は、帰属意識が薄れワークシェアができるようになり「管理しやすくなった」という評価でした。
もう一つの事例は、高齢化した古いA施設(拠点)と若手しかいない新しいB施設(拠点)の半分を入れ替え、年齢構成を平準化したという事例です。 ベテランと若手がバランスよく機能するようになり、「離職率が下がった」という評価でした。
もしかすると、セミナーの為に成果を大袈裟に吹聴している可能性もありますし、別の法人で、同じことをやったら反発されて離職率が上がる可能性もあります。
赤字が続いたある法人は、経営改善に取り組み、数年の黒字化に成功しましたが、やり方が良くなかったようで、職員に反発され大量退職の結果、職員配置ができなくなり、収益が激減して破産に追い込まれたと言われている社会福祉法人があります。全くの本末転倒です。
ただ、管理職を長く放置したり、年齢構成が偏ったりするとあまり良いことは起きないという問題は想像がつくと思います。ポイントはアクションプランに対する因果関係です。
そうか「その手があったか!」という気付きを一つでも多く手に入れて下さい。
社会福祉法人向けセミナー受講の落とし穴
ありがちな誤解で、筆者も気が付くまでにかなりの時間がかかったことです。
セミナーの講師は情報の発信機で、セミナーの受講者は受信機としましょう。 発信機の性能は、いつの時代もそんなに変わりませんが、受信機の性能は大きく変わります。発信機は完成度の高いプロレベルの限られた方で、受信機は発展途上の試行錯誤中の多数の方であるためです。
例えば、経営改善の前の状態と経営改善中の状態では、同じことを聞いても拾える情報が異なります。受講者が経験により大きく進化する為です。
一番大きな誤解は、あのセミナーは一度聞いたから大丈夫という慢心です。
東大首席弁護士の山口真由氏は「7回読み」という身に着け方を推奨しています。1回目と2回目では捉えられる情報が違うと言っています。
セミナーを7回受講して下さいとは言いませんし、聞けば聞くほど効果が上がるものでもありません。ただ、1回聞いたので終わりで良い。2回目は意味がない。という姿勢でなく、繰り返し受講し、聞き手のタイミングに合った情報を入手することが成功の秘訣であるということをご理解頂きたいのです。
受講者のニーズは日々変化しています。
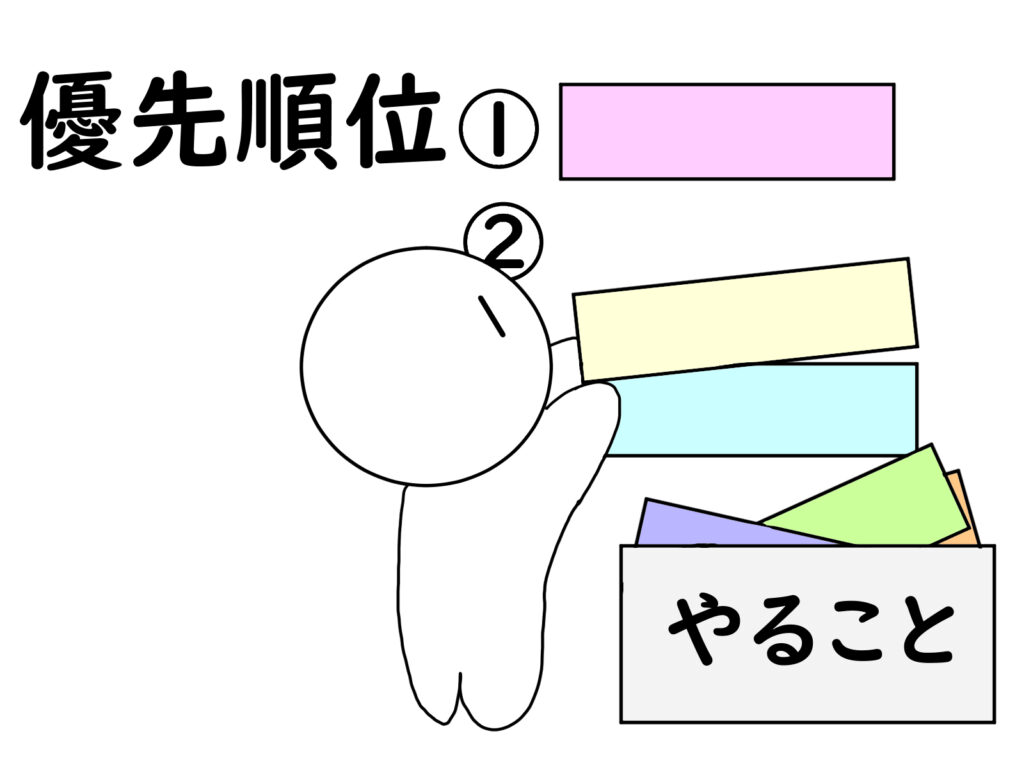
まとめ
社会福祉業界のセミナー活用術についてご紹介してきました。
(1)無料セミナーと有料セミナーは講師が言える範囲が異なります。
(2)目的意識を明確化してから受講するセミナーを探しましょう。
(3)能動的に欲しい情報を取りに行きましょう。その手があったかという気付きが欲しいです。
(4)セミナー受講に関するありがちな落とし穴に落ちないように注意しましょう。
繰り返しになりますが、貴法人は唯一無二ですので、他法人のやり方が通用するとは限りません。法則には貴法人だけに通用する個別法則とどこの法人にも通用する普遍法則があり、セミナーで個別法則は手に入りません。普遍法則と思われる情報をアレンジして個別法則に昇華させる必要があります。
経営改善は、どんなに準備しても成功するとは限りませんし、必ず抵抗されますので、言うほど簡単ではありませんが、成功率を上げるためにセミナー情報は有効です。
筆者も、実務で実際にクライアントである社会福祉法人の経営改善に取り組んでいますし、あちこちの団体で研究会に参加したり、社会福祉法人向けのセミナー講師を引き受けることがありますので、いつか皆さんと会場でお会いできたら幸いです。

