社会福祉法人専門の税理士と一般的な業務を行う税理士の違いを解説
「税理士なら、誰に頼んでも同じではないか?」 そう思われるかもしれませんが、実は税理士の世界は「医者の診療科目」に非常によく似ています。
内科、外科、眼科……。医師免許は共通でも専門が分かれているように、税理士も「一般企業」と「社会福祉法人」では、求められるスキルが全く異なります。
今回は、社会福祉法人専門の税理士と一般的な税理士の「決定的な3つの違い」と、なぜ専門家が少ないのかという業界の裏側を解説します。
目次
前提となる税理士の登録根拠と特徴
税理士になるためには、税理士登録をしなければなりません。あまり知られていませんが、その登録根拠は異なり、各々特徴があります。
登録根拠の違い
(1)税理士試験で必要な5科目を全て合格する。(税理士試験だけで合格する。)
(2)税務署に職員として勤務し、税理士試験の全部又は一部を免除申請する。(税理士試験を受験する方もいますが、年数によっては税理士試験に合格しなくても登録可能です。)
(3)大学院で修士論文を書き、国税庁の論文審査を受けて、税理士試験の一部の免除申請をする。(現在は以前と異なり、税理士試験の会計科目と税法科目に必ず合格する必要があります。)
(4)公認会計士が税理士登録する。(税理士試験に合格しなくても登録可能です。)
(5)弁護士が税理士登録する。(税理士試験に合格しなくても登録可能です。)
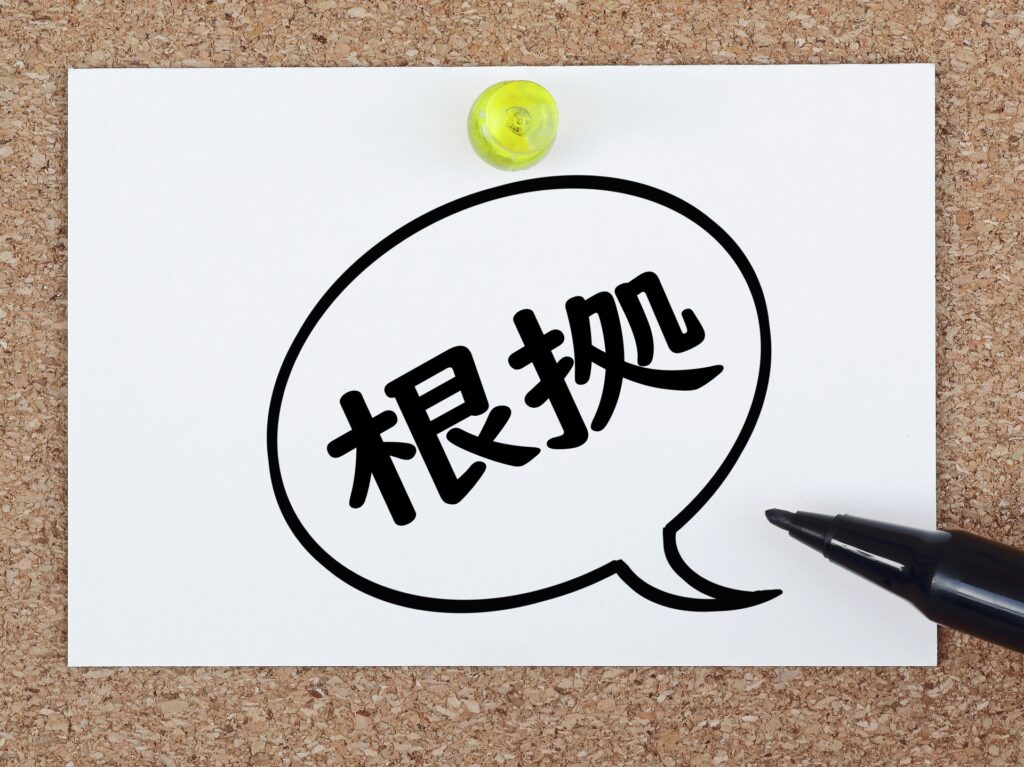
登録後の特徴
ほとんどの税理士は上記の登録根拠となり、登録後にそれぞれ特徴が出ます。
(1)は、会計や税法の知識が正確に身に付いており、王道といえます。
(2)は、税務署の実務に最も精通しており、税務調査が得意です。
(3)は、税理士試験による会計や税法の知識に加え、学説や判例などの研究をしています。唯一と言って良いくらい、社会福祉法人会計や税務に関する研究が本人の意思で可能です。
(4)は、監査能力があり、法定監査や内部統制に詳しいです。監査人監査を受ける大規模法人にお勧めです。
(5)は、行政法に詳しく、税務訴訟手続きや民事訴訟もできます。訴訟を想定している法人にお勧めです。
これらの特徴を踏まえて、税理士に何をしてもらいたいのか?が税理士を見極めるポイントになります。
社会福祉法人専門の税理士と一般的な業務を行う税理士の3つの決定的な違い
上記で、まず前提となる税理士の登録根拠が異なる事をご紹介いたしました。
それらを踏まえ今回の本題である社会福祉法人専門の税理士と一般の税理士のスキルの違いを3つほど簡単に解説してまいります。
1.会計基準の知識と経験が違う
社会福祉法人は会計基準が企業会計とは異なります。企業会計は企業会計原則といってルールによって処理しますが、社会福祉法人会計基準は政令で強制力のある法令です。
例えば、法人内の内部取引は企業会計では管理会計といって、開示義務がなく、法人が自主的に行う領域ですが、社会福祉法人は制度会計として定められ、開示義務があり、任意性がありません。
決算書や勘定科目も企業会計より数が多く、知らなければならないルールが企業会計より多いという違いがあります。
社会福祉法人専門の税理士はこの知識と実務経験が圧倒的に違います。
2.公の支配下規制の知識と経験が違う
株式会社は自分で売り上げを稼ぎますが、社会福祉法人は、補助金や助成金などたくさんの公金が入っています。
実は、憲法89条では「公金を私的団体に支出すること」を原則禁止しています。 社会福祉法人がこの禁止規定に触れないよう、国は社会福祉法人を「公の支配(管理)」下に置きました。民間でありながら行政に近い厳しい管理を受ける―この特殊な立ち位置を理解していないと、適切な運営アドバイスはできません。
社会福祉法人専門の税理士はこの知識と実務経験が違います。
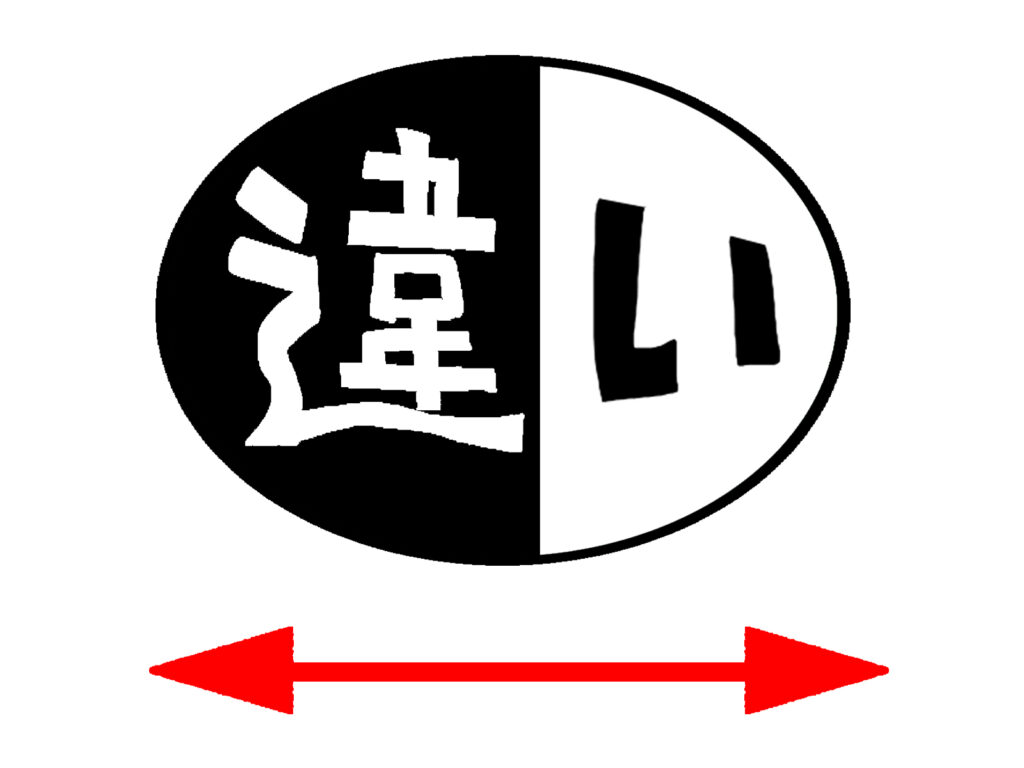
3.税務上の知識と経験が違う
法人税法では、社会福祉法人は公益法人等といわれ、収益事業のみ課税されます。しかし、社会福祉法の収益事業と法人税法の収益事業はイコール関係になく、どの部分が課税かという課税領域の特定が難しいという特徴があります。
また、消費税法も社会福祉法人が行う社会福祉事業に係る事業は原則的には非課税ですが、その非課税そのものの特定に加え、社会福祉事業でなくても社会福祉事業に類する事業として非課税とされるものもあり、株式会社に比べ、課税領域の特定が難しいという違いがあります。
更に、特定収入の調整計算など社会福祉法人に独特の規定もあります。
社会福祉法人専門の税理士はこの知識と実務経験が違います。
なぜ「社会福祉法人専門」の税理士は少ないのか
社会的な意義があり、これほど特殊であるにもかかわらず、専門の税理士が少ないのには理由があります。
国家試験の制度は、税理士になるまでは、いわゆる一般税務と言って、広く一般的な株式会社や個人の税務申告など日本全国共通の業務を行うことが想定されています。
しかし、税理士になると途端に、「税理士として生き残っていくためには、特化して付加価値をつけよ」と言われます。そして、それが特化の生まれる主たる理由でもあります。
特化するといっても様々です。例えば、相続税に特化する会計事務所がありますが、上記の登録の過程で徐々に相続税にシフトしていくことが可能です。「一般税務から相続税」という形が過程で成立可能です。
しかし、上記の過程で特化できない領域もあります。
社会福祉法人会計はその典型で、その過程ではほとんど触れることができません。したがって、もし特化を望むなら、一般的なスキルは実務で独自に身に着けるしかないですし、特定の論点を科学的に研究したいなら大学院に行くしかありません。
身に付ける選択肢が少く、クライアント数も少ないことから、税理士にとってコスパの良くない投資になるため、専門の税理士は少ないことになります。その中で敢えて、社会福祉法人専門を掲げている税理士は相応の覚悟を持って取り組んでいるはずです。
まとめ:失敗しない税理士選びのコツ

ここまで、社会福祉法人専門の税理士と一般的な税理士の違いについて解説してきました。
社会福祉法人の会計と税務は、税理士になるための過程ではほとんど学ぶことができない「特殊な領域」です。そのため、多くの税理士は開業後に独学で身につけるしかありません。
身に付けるといっても、覚えることは山ほどあるのに、一般企業に比べてクライアント数は限られます。 つまり、税理士側からすると「わざわざ苦労して特化するメリットが少ない」という現実問題もあります。
「一般的な税理士でも対応できるか?」という問いに対し、私は経験上、「制度上は可能だが、リスクを考えると現実的には避けるべき」だと考えています。慣れない会計処理によるトラブルは、法人の社会的信用にも関わるし、そのような事例を見てきているためです。
失敗しないパートナー選びのために、以下の3点を必ずチェックしてください。
- 「専門」の実績が可視化されているか
事務所のホームページやパンフレットで、明確に「社会福祉法人専門」と標榜しており、受託件数や継続年数の実績が示されているかを確認しましょう。 - 担当者の専門性と経験値
「資格の有無」と社会福祉法人の実務にどれだけ深く関わってきた担当者を付けてもらえるか確認してください。 - セカンドオピニオンの検討
「今の税理士さんとの付き合いも大切にしたい」という場合は、大局的な判断や指導監査対策だけを専門家に依頼するセカンドオピニオンの活用も有効な手段です。
「餅は餅屋」の安心感を
税理士も医者と同じで、専門分野によって提供できる価値が大きく異なります。同じ顧問料を支払うのであれば、リスクを未然に防ぎ、法人の経営を支えてくれる専門家を選びたいものです。
当事務所では、全国の社会福祉法人に精通した税理士ネットワークを構築しており、貴法人に最適な税理士をお繋ぎするサービスも展開しております。
「今の体制で大丈夫か不安」「専門の税理士を探している」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。貴法人の安定した運営を全力でサポートいたします。

