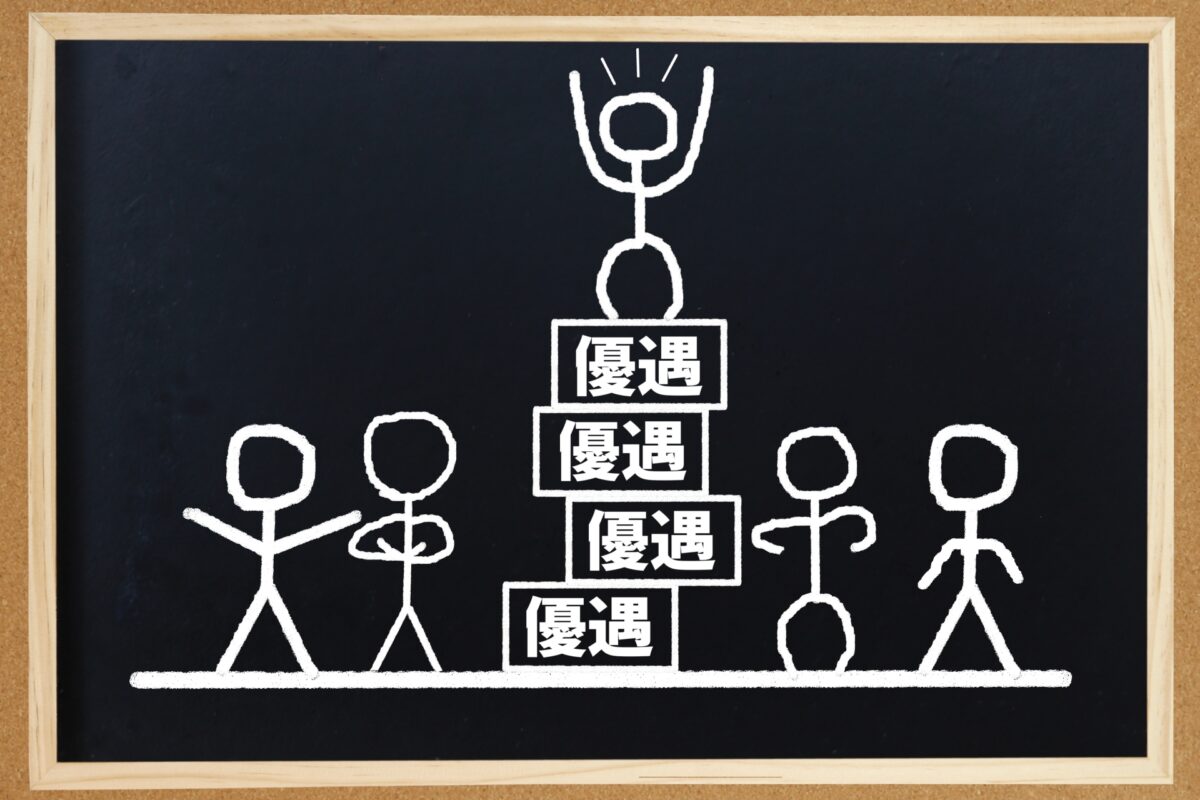社会福祉法人が受ける税制優遇措置を税理士が解説
社会福祉法人は公共性や非営利性の性格から、税制面でかなり優遇されている法人であることは皆さんご存じだと思います。
優遇といっても、株式会社などの営利法人に対する優遇とNPO法人など他の公益法人等に対する優遇の2つの視点があります。
今回は、面倒な手続きが必要ない簡単で効果的な優遇規定を5つご紹介します。
目次
簡単で効果的な優遇措置とは?
まず、簡単でない優遇措置からご理解頂きたいのですが、例えば、以前紹介した寄付金の税額控除や土地を譲渡した場合の5,000万円の特別控除などは、効果的でありできれば使いたい規定です。
しかし、この規定を使うための手続きが非常に煩雑で要件も厳しく、使いたいと思ったけれど、面倒なので諦めるという法人が多いのです。
私自身も、今までそのような経験が何度かあります。
一方で、手続きなして簡単に使える優遇規定もあります。このような規定は知っているだけで使えるので逃すべきではありません。

1.法人税法の収益事業規定
公益法人等は収益事業を行う場合に法人税の課税対象となり、法人税が定める34事業を行うと法人税が課税されることはご存じかと思います。
34事業の一つに医療保健業というものがあります。したがって、一次判定では公益法人等であっても病院事業や介護事業を行うと収益事業として課税されるということになります。
しかし、社会福祉法人が行う医療保健業は収益事業には該当しないという優遇規定がありますので、二次判定で社会福祉法人は(その医療保健業について)課税されないということになります。
社会福祉法人というだけで利用可能で他に要件がありません。
これは非常に大きな優遇規定で、この規定により社会福祉法人は、多くの事業が非課税になっている実態があります。
同じ公益法人等であるNPO法人の介護保険サービスなどの医療保健業は課税です。他の公益法人等に対しても優遇と言えます。
2.法人税法の税率
営利法人や公益法人等は、その法人の種類によって法人税の税率が異なります。
現在の規定は、所得が年800万円を超えると、多くの法人の税率は23.2%ですが、社会福祉法人は19%です。
この規定は、社会福祉法人であるだけで利用可能で他の要件はありません。税務申告ソフトの設定(法人の属性の選択)を誤らないことに注意しましょう。

3.法人税法のみなし寄附規定
公益法人等が収益事業から収益事業以外に資金を移動した場合は、本来は内部取引で税金の計算に影響はありませんが、外部取引の寄付金とみなして経費として損金算入ができることはご存じかと思います。
法人内部の資金移動を経費(損金)にできますので、大きな優遇です。
実は、公益法人等の種類によって、みなし寄付金の限度額に差があります。
社会福祉法人は、寄付前所得の50%と年間200万円までのどちらか大きい金額まで認めてもらえますので、公益法人等の中でも限度額が大きく有利といえます。
この規定は、社会福祉法人であるだけで利用可能で他の要件はありませんが、みなし寄附は現金主義なので、3月31日までに現金を動かす必要があります。予測(概算)で動かさないと、決算整理中の5月では間に合いませんので注意して下さい。
4.印紙税の非課税規定
社会福祉法人は、社会福祉法人であるという理由で印紙税が非課税になる場合があります。
社会福祉法人が発行する領収書→営業に関しない受取書に該当するため非課税(印紙税法 別表第一 課税物件表 17号文書)
この規定は、社会福祉法人であるだけで利用可能で他の要件はありません。
社会福祉法人でも領収書を発行するシーンはたくさんありますので、この規定により非課税になるケースは非常に多いです。
ただし、社会福祉法人の全ての印紙税が免除されるわけではなく、契約書などの印紙税は他の法人同様に課税されますのでご注意下さい。

5.住民税の非課税規定
社会福祉法人が収益事業を行って課税される場合、国に納める法人税と都道府県や市区町村に納める住民税や事業税が発生するのはご存じかと思います。
これらの税金は所得が生じていると税金が発生する仕組みになっていますが、住民税だけは特徴的な税制優遇の仕組みになっています。
社会福祉法人は、所得の90%以上をみなし寄附として社会福祉事業に充てていれば住民税は完全に非課税にできます。
非課税判定票の提出により、どんなに多くの所得が発生していても内部取引だけで非課税にできる。これは、法人税や事業税にはない特徴です。
経験上の留意点は、住民税の非課税規定を狙い90%をみなし寄附すると、法人税のみなし寄附の限度額が50%なので、40%分が否認され、それをどう考えるかという問題が生じます。
税金を減らすという観点だけで言えば90%が正解ですが、施設への指導検査が入らない収益事業拠点で40%分を残して自由にお金を使いたいという希望があれば50%が正解になります。
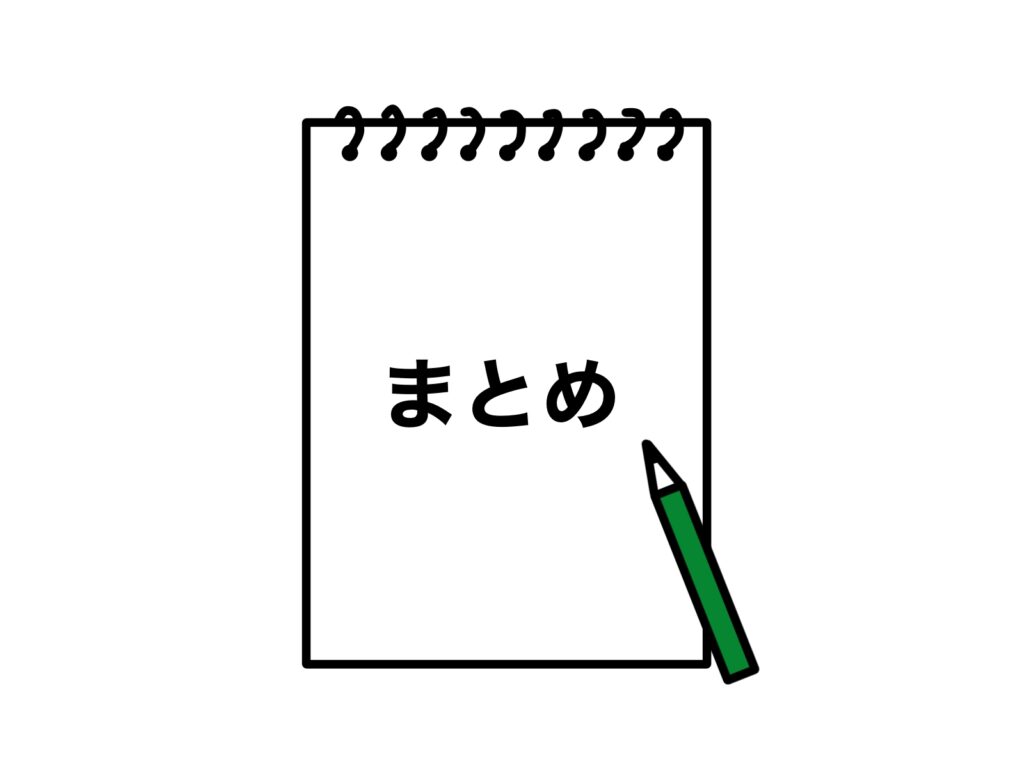
まとめ
社会福祉法人の税制優遇は消費税や固定資産税などは有名ですが、今回ご紹介した規定は、地味ですが簡単に使えて効果の高い税制優遇です。
(1)医療保健業を課税申告しないで下さい。
(2)税率の設定を誤らないで下さい。
(3)みなし寄附は限度額まで活用して下さい。
(4)領収書に印紙を貼る必要はありません。
(5)住民税の非課税判定表を提出して非課税にして下さい。
社会福祉事業は2000年以降、措置から利用契約制度に移行し、株式会社などの事業会社も社会福祉法上の社会福祉事業に参加できるようになりました。
同じ事業をして、一方の社会福祉法人は非課税で、他方の株式会社は課税なのは、不公平なのではというイコール・フッティング議論が出るようになりました。国民感情としては当然なご意見です。
しかし、現行法規はまだたくさんの社会福祉法人の税制優遇がありますので、その優遇を最大限活用し、利用者に対してより良いサービスを行うことができる可能性があります。
税制優遇は知らないと使えないこともありますので、税理士の力を借りて是非ご活用頂くことをお勧めします。
当事務所は、社会福祉法人専門の会計事務所で、税制に対する数多くの実績があります。社会福祉法人の税制に興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。