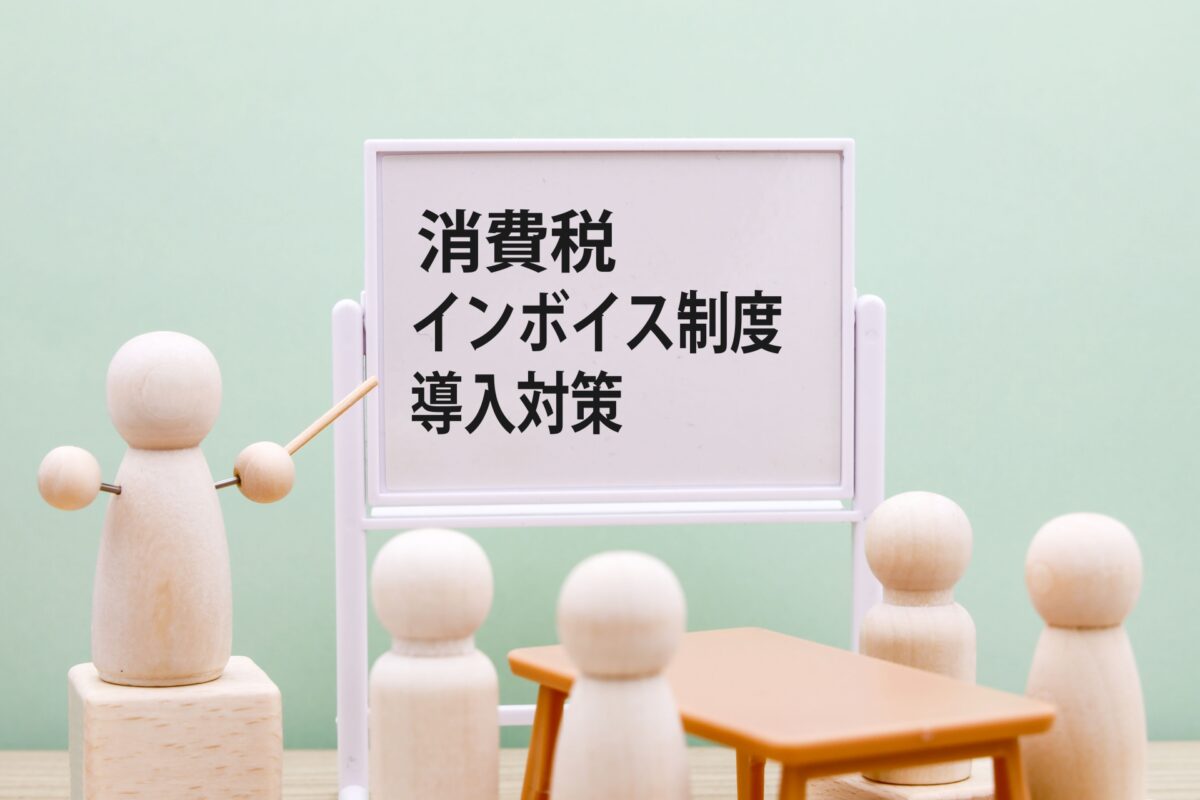社会福祉法人がインボイス対応で気を付ける事はありますか?
インボイス制度は、令和5年10月から始まり1年以上が経過しましたので、かなり定着してきました。
社会福祉法人は、全く影響のない法人も多く、心配されていた程には現場は混乱しなかった印象があります。
社会福祉法人とインボイス制度について、厚生労働省から通達された追加の注意事項を含め、もう一度気を付けることをまとめておきたいと思います。
目次
インボイス制度で変わった点
以前のいわゆる「帳簿方式」から今回の「インボイス方式」で変わったことは、仕入れ税額控除の要件にインボイス番号が加わり、請求書や領収書などの証票にインボイス番号がない場合、証票をもらった人が仕入れ税額控除できなくなるということです。
また、消費税の集計の方法が取引ごとでなく請求書等1枚につき取引を合計して1回で行うように変更した2つの点が大きく変わった点です。
免税事業者はインボイス番号を発行できない(=制度として仕入れ税額控除させないようにした)ということが最大のポイントです。
社会福祉法人は免税事業者が多いため、インボイスを発行できない法人が多いということになります。
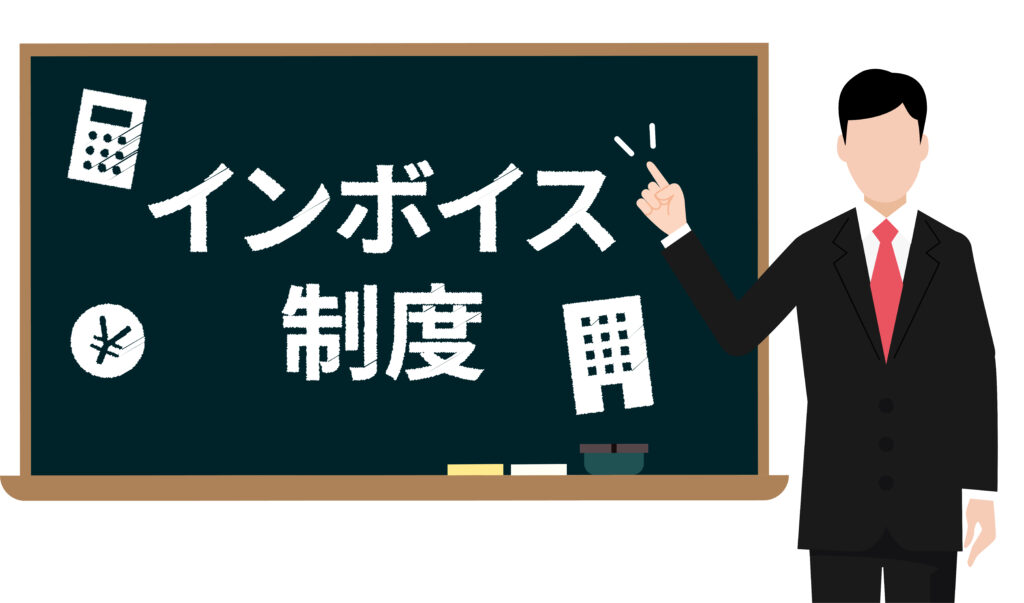
社会福祉法人への影響
消費税の影響は売上側と仕入れ側の両方で影響を考える必要があり、インボイスも同様です。
売上側の影響
インボイス制度は課税取引の話で、社会福祉法人は非課税取引や免税事業者が多いため、比較的インボイス制度の影響は少ないといえます。
影響のある社会福祉法人の課税売上の代表例は、以下のようなものです。
(1)就労支援施設の生産活動売上
(2)従業員など利用者以外の給食事業収益
(3)収益事業の事務所などの不動産賃貸収益
当法人が発行する請求書等にインボイス番号が無いと困る人がいるか否かで検討すると良いと思います。
就労支援施設の生産活動が、例えばカフェのように一般消費者しかお客さんが来ない場合は、インボイス番号がなくても困らない人が多いです。しかし、清掃事業のように事業者向けのサービスを展開している場合は、お客さんが当法人の関連法人の場合は理解が得られますが、そうでない場合インボイス番号がないと困る方が多いことになります。
利用者以外の給食事業収益は、ほぼ従業員などで、お客さんに事業者はいないため、インボイス番号がなくても困らない方が多いです。
収益事業の不動産賃貸収益は、居住用の場合は非課税ですので影響がありませんが、事務所用の場合、インボイス番号がないと借主である事業者が困ることになります。
このように、売上の種類ごとに影響を考えておく必要があります。
仕入れ側の影響
社会福祉法人の場合、当法人主催のイベントに個人事業主である講師やインストラクターなど招聘して行う場合や個人との業務委託など、免税事業者との取引は一定数あります。
以下のような視点で、影響を考えると良いと思います。
(1)原則課税の場合
本則課税の場合、個別対応方式にしても一括比例配分方式にしても、免税事業者からの仕入れは、インボイス番号のない取引は、番号のある取引と区別して会計帳簿に認識する必要があります。
(2)簡易課税の場合
社会福祉法人の場合、比較的簡易課税方式を採用している法人が多いと思いますが、簡易課税の場合は、免税事業者からの仕入れは、結果的に影響がありませんので、無視することができます。

社会福祉法人はインボイス番号を取るべきか?
結論は、法人によってケースバイケースです。
この悩みは、普通に判定すると免税事業者である法人だけです。そもそも課税事業者は、悩む必要はありません。
免税事業者は納付税額が発生せず、課税事業者は多かれ少なかれ納付税額が出ますので、免税事業者を選択できるなら有利となりますので可能であれば選択すべきでしょう。
ただし、インボイス番号を発行しないと困る人が出る場合、その影響を考えた上で、課税事業者登録をしてインボイス番号を発行しましょう。 場合によっては、得意先と取引ができなくなってしまう恐れがあります。
課税事業者を登録してもいわゆる2割特例や、登録しなくても段階的な税額控除否認などの経過措置もありますので、投稿日現在では、影響を緩和できる制度が用意されています。
インボイス制度による社会福祉法人会計への影響
インボイス制度導入により令和5年3月22日に社会福祉法人会計のQ&Aに追加がありましたので要点を紹介しておきます。
問2-2税込み方式の継続
Q、現在の税込経理方式をインボイス制度導入後も継続できるか?
A、できる。
問2-3税込み方式から税抜き方式への変更
Q、計算書類の取り扱いは?
A、実務上の煩雑性から、変更初年度の期首より前に取得した固定資産等の取得原価から消費税相当額を控除しないことができる。 また、計算書類の注記についても法人の負担を考慮して影響額を記載しないことができる。

まとめ
社会福祉法人は非課税売上が多く免税事業者が多いです。簡易課税を選択している法人が多いのも特徴的です。
社会福祉法人は株式会社に比べ、インボイスによる影響は少ないと言えますが、法人によっては影響があります。特に就労支援事業で生産活動を行っている法人は影響が大きいので要注意です。
売上は、請求書や領収書を渡す人がインボイス番号を必要とするか否かという観点で検討する必要があります。
仕入れは、免税事業者との取引を無視できるかがポイントです。
免税事業者がインボイス番号を取ると、免税事業者から課税事業者になるため劇的に運用が変わります。
影響を考えたり、その影響によってインボイス登録をすべきか否かの意思決定をしたりすることは簡単でないので、知見のある税理士の力を借りて検討することをお勧めします。
当事務所は、数多くの社会福祉法人の実績があります。インボイス制度で、お悩み事があれば、お気軽にご相談下さい。